- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
2030年に、自動車産業は大きな変化を遂げているだろう。「モビリティー革命」の到来である。それは既に起こり始めている。
本書の前半では、モビリティー革命を引き起こす要因として、
(1)パワートレーンの多様化
(2)クルマの知能化・IoT化
(3)シェアリングサービスの台頭
──という三つを挙げる。その上でこれらの要因が、「現在の自動車産業をどのように変えていくのか」という点について詳しく分析する。
本書の後半ではこれら三つの要因が自動車産業に与えるインパクトについて、数字を挙げながら考察する。「乗用車メーカーの利益が半減」「部品産業存亡の危機」「ディーラー数が7割減る」──など、そのシナリオは衝撃的である。
日本経済の根幹を支えてきた自動車産業は、こうしたモビリティー革命の激流に翻弄されるのではなく、“革命の指導者”となって今後の熾烈な競争を勝ち抜くことが求められる。本書の最後では自動車産業への提言として、生き残りに向けた具体策を示している。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
30
ZEVとは、Zero Emission Vehicleらしい(19頁折れ線グラフより)。で、これが普及してCO2が普及するらしい(17頁折れ線グラフ)。専門用語の註は、冒頭か、脚注に書いておいてほしい。 AIの進化でディープラーニング(32頁)。 ライドシェアに移行するのは、1000㎞。保有のままは1万2000㎞という(60頁図4)。 未来デバイスビジネスは、生活者・社会、動く何か、コトづくり、利巧に稼ぐ、コラボレーション(213頁)から成る。 2017/11/14
ハッシー
15
★★★☆☆2017/11/16
tokkun1002
14
2016年。モビリティ社会。自動車産業が変わる。サプライヤー系列崩壊。確かに始まっていると思う。時期と程度をどう読むか。そして、どんな作戦をとるかが結果を決める。数年前、ガソリンが枯渇すると言われていた、今では数千年は問題ないことが分かっている。電気自動車は、航続距離と充電時間の解決に時間がかかり、まだ数年はセカンドカー止まりだろう。運転支援システムは普及しつつあるも完全自動運転には法の壁もあり当面無理だ。そんなことからこの本に過敏に反応するのは良くないと思う。2017/01/06
あつ子🐈⬛
6
本の整理をしていて発掘。2030年までは捨てずに持っていようか…2025/08/01
前田まさき|採用プロデューサー
6
■2050年代には次世代が100%?/今後、中国やインドでのモータリゼーションを受け、CO2の排出量は現在の2.5倍になると想定される。それを受けると、2030年には4台に1台、2050年までにはすべての車両を次世代車にする必要がある ■ディスラプターが主導するクルマ産業の破壊/要素技術を提供するエキスパートは、大企業に限らずスタートアップ企業も一翼を担う。プラットフォーマーにとっての顧客は、自動車ドライバーだけではなく、移動ニーズを有するすべての人2020/04/06
-
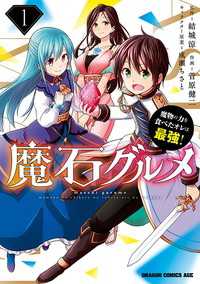
- 電子書籍
- 魔石グルメ 魔物の力を食べたオレは最強…
-
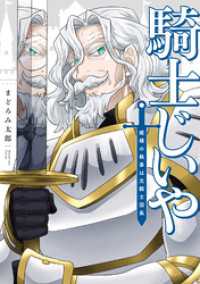
- 電子書籍
- 騎士じいや 姫様の執事は元騎士団長 【…
-

- 電子書籍
- ユカをよぶ海 (2) コルク
-
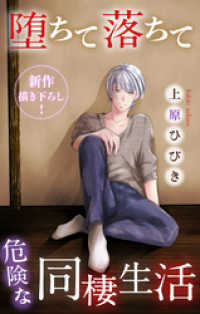
- 電子書籍
- Love Jossie 堕ちて落ちて危…
-
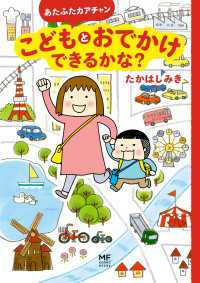
- 電子書籍
- あたふたカアチャン こどもとおでかけで…




