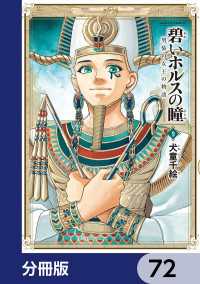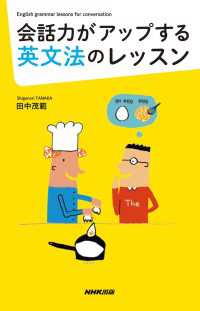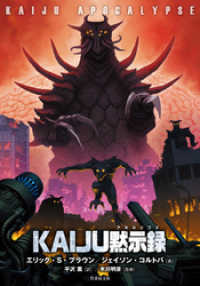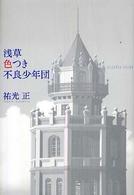- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
文章はざっくりと三つの型に分けることができ、それぞれに「こうすればうまく書ける」というパターンがある。論理的な「主張型」の文章では、「問題→解決→根拠」の構成が読者にとって親切であり、接続詞「そして」は使わないほうがいい。物語や経過報告は「ストーリー型」に属し、小説では情景や行動の描写によって人物の心情を示すといった手法が用いられる。三つ目はエッセイなどの「直観型」。エッセイとは個人的体験から感想、そして直観的でかつ普遍的な思考、ものごとの本質を語るものである。直観は意外に間違えないから、論理的でなくとも人々を納得させることができるのだ。自己流にこだわった文章は未熟なものになるおそれがある。型というルールを学び、その上で自らの個性を発揮しよう! 文章指導のプロだから書ける実践的文章読本。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAKAPO
30
文章の型を「主張型」「ストーリー型」「直感型」に分け、それぞれの型を解説している。「主張型」の代表は論文、問題に対する解決、つまり意見を言う文章だ。問題+解決+根拠という三つの要素がそろっていればよいのだ。「ストーリー型」は、具体的な場所・時間で登場人物が行動する。事件が起こり、意外な方向に話は転がっていく。「直感型」は、エッセイや随筆だ。その構造とは、体験・感想・思考の三点セットである。文章を書くときには、どんなタイプが求められているかだけでなく、どんなタイプが自分に合っているのかも自覚する必要がある。2020/06/14
4492tkmt
11
主張型文章、ストーリー型文章、直観型文章を書く型が紹介されています。文章を書くにも、ルールや型、技術がいるってことをあらためて、感じました。また、書く技術がそのまま、文章を読むときの技術にもつながっていて、大変参考になりました。が、これを読んで、すぐに読メの感想がうまく書けるようになるわけではありません。私のレビューに、特に改善が見られなくても、この本の価値が下がるわけではないので、誤解のなきよう、よろしくお願いします。2022/04/09
みどるん
8
一概に文章とはいえどタイプによって求められるものが異なると、分かってはいても解説されて気付くことが多い。ストーリー型の情景描写と心情描写など普段無意識下に置いていることを客観的に見ることができた。Pointのまとめも分かりやすく、種々の小話としてもおもしろかった。特に花。2013/12/07
トーマ
7
図書館本。文章力強化月間。三冊目。2018/02/08
hk
7
本書の眼目は「随筆・エッセイとは何なのか?どういう構造になっているのか?」だ。一般的には、思いのまま筆のいくままに書き綴るのが随筆・エッセイであり「自由で簡単そうだよね」という社会的偏見すらある。ところがどっこい実際にはそんな生易しいものではない。 では随筆とは何か? 随筆とは、自らの体験・感想をもとにしてそれらを深い思考によって普遍的な何かとリンクさせて読者の共感を得るという野心的な試みなのだ。手短に随筆・エッセイの根幹部分をまとめると「体験⇒感想⇒思考⇒ユニバーサル化」である。ここで留意したいのが随筆2016/08/04