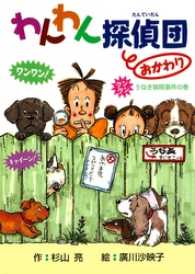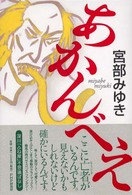内容説明
生命誕生から約40億年。変化は常に一定ではなく、爆発的な進歩を遂げる奇跡的な瞬間が存在した。眼の誕生、骨の発明、あごの獲得、脚の転換、脳の巨大化……。数多のターニングポイントを経て、ゾウリムシのような生物は、やがてヒトへと進化を遂げた。私たちの身体に残る「進化の跡」を探りながら、従来の進化論を次々と覆す、目からウロコの最新生物学講座!
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
283
第1章「膜」では、生物とウイルスの境界を、家を例に挙げて説明しており、門外漢にもきわめて分かりやすいものであった。また他の章のいずれも、わかりやすさという点では、これほど平易に解説したものも見当たらないほどだ。ただ、タイトルから期待した「爆発的進化」は第3章の「骨」で、「動物を食べる動物が現れたことが、カンブリア爆発の引き金になった」とするだけで、意外にもさらりと通り抜けてしまう。ダーウィンの考えていた漸進的な進化を打ち破る、「爆発的進化」をこそスリリングに書いてほしかったというのが素人読者の望みだ。2017/06/29
まーくん
96
生物進化について教科書とは違った切り口で易しく説明。思わず”なるほど”と頷いてしまう。生物の各パーツごとの章建て。例えば「口」動物とは口のある管だ。「眼」カンブリア爆発と捕食者の出現。「脚」魚の脚は何をするのか…などと進化に纏わるエピソード(小ネタ?)を集めることで、進化全体の原理を見通す。生物の「セントラルドグマ」によると遺伝情報はDNA→RNA→タンパク質と流れるが、DNAはタンパク質でできている。一体、どっちが先なのか?結論は出ていないがRNAが鍵を握っているという説もあるとか。興味は尽きない。2020/09/12
mae.dat
77
すすーと読めた。例えが楽しい。一番たのしいのが、最初の「細胞は暖かい家である」「ウイルスはただの掘っ建て小屋」。なんか笑ったね。(๑⃙⃘´ꇴ`๑⃙⃘)。最初が秀逸だったから、それを超えられなかったけど、他も面白くて、脚の章での振りを脳の章の締めで回収したりね。あとあれ、”単細胞生物が使い捨ての細胞を発明したとき、それが多細胞生物の始まりだったのだ“ってのは、膝を打ったね。 講義もきっと楽しいんだろうな〜♪。2020/05/29
ホークス
50
構造や原理から生物進化を語るエッセイ。簡潔で分かりやすい。例えば「膜」の話。生物の細胞膜は物質の出し入れが可能であり、ウイルスはこの点で生物とは言えない。出し入れは水と油の原理というのも驚き。進化に特定の方向性など無いのは間違いない。人は色覚を一旦失い、猿になってから再度獲得している。魚類から両生類への四肢の進化は上陸の為ではなかった。直立歩行になるだけで脳が大きくなる訳ではない。ほとんど偶然、プラス僅かな差異によって生き延びたのが今の生物だ。そう考えると、多様性がより愛おしく思えてくる。2019/04/13
AICHAN
44
図書館本。進化とは種を超えること。しかし、生物に対していくら人為的な措置をしても種を超える突然変異は起きない。ショウジョウバエはショウジョウバエのままなのだ。このことからも、進化論が正しいとすると何十億年もの間に単細胞生物の前段階からヒトができるまでには、1%どころかもっと低い確率の何かが起こり生物は突然変異を繰り返してきたのだ。というような内容を期待したのだが、タイトルのようなことは書かれていない。読みやすくてわかりやすい講義を聴いているような好著だが、そういう意味では期待はずれだった。2017/07/20