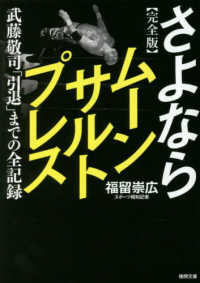内容説明
「今、世界は戦争に向かいつつあります。
私は本書のはじめに、あえてそうはっきりお伝えしようと思います。」
(「はじめに」より)
戦争に対する立場には、大きく分けて2種類の立場が存在します。
一つは、「国家は互いに協調すべき」と考える〈リベラリズム〉。
もう一つは、「国際社会はパワーゲームだ」と考える〈リアリズム〉。
この対立する2つの立場のいずれもが、戦争それ自体を望まないにもかかわらず、
残念ながら戦争を止めることはできないと、著者は指摘します。
では、何が戦争を止めるのか。
現場(海上自衛隊部隊指揮官)と研究(東京財団研究員・制作プロデューサー)の
両方を知り尽くした著者の提言「日本だからこそできること」には、
戦争のない世界を実現するために、これから日本が向かうべき方向が示されています。
●目次
第1章 世界中で「理想の崩壊」が起こっている
第2章 リベラリズムとその限界
第3章 リアリズムとその限界
第4章 柔らかいリアリズムへ
第5章 理想論抜きで戦争を止める方法
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
新父帰る
9
何が戦争を止めるのかを分析する方法として、リベラリズムからのアプローチとリアリズムからのそれを比較。リベラリズムは理想を掲げ、戦争を善悪で色分けしてしまう為に袋小路に入り込む。一方、リアリズムは国際社会の無政府状態、国益、パワーの三つの要因で伝統的な説明してきたが、これらだけでは戦争を止める理論の構築が出来なかった。そこでネオリアリズム、つまり国際システムの変化を導入。しかし、著者はこれでも不十分ということで「欲望の体系」理論を導入。経済発展という人間の根源的な欲望を因子に加えて戦争を止める試論を提唱。2016/09/27
こひた
5
あっさり分量の割に専門家らしいレベルK思考の深さなのだが,タイトルの課題は「簡単には無理!」って悲しい結論。リベラルの失敗はフィーチャーされるがリアリスト側もまだまだ進歩が必要なのはそう。雑な発想だが,同質性が高く言語習得が難ありな日本に安易に難民誘致してカッコつけるより,潜在的難民発生リスクを下げる支援を頑張りそれを乱暴にいうとCO2排出量取引みたいな枠組みで評価してもらうほうが,実際は本国で頑張ったほうが夢も希望もあったのに無為に過ごしました名目研修生で搾取されましたで終わるより3方得なのではと。2025/05/08
やまと
4
人類の歴史は戦争の繰り返しで、国やテロ組織の戦いは止むことが無い。世界は戦争に向かいつつあるという筆者の見方に同感する。また、リアリズム(国家はパワーと安全を求める)は過去を分析するツールで、リベラリズム(国家は互いに協調すべき)は未来はこうあるべきという方法論という見方もわかりやすい。分析と理想論では戦争を回避できず、経済的欲望に答え不満を緩和させて「戦争しない方が得」と思わせることが戦争を止めさせる方法と主張している。日本人は戦争という言葉を嫌い、戦争について深く考えてきておらず、直視する必要がある。2016/10/08
ロスリスバーガー
2
「何が戦争を止めるのか」よりも先に「何が戦争を引き起こすのか」というところから考察。「リベラリズム」と「リアリズム」の双方について、その性質について言及しているが、そのまんま現状の左右両翼に象徴されている部分が大きい。ただ今の日本では互いが全く相容れない状況が続いているが、そうではなく本書の立ち位置のように、左右双方に目配りできる視点をすべての国民が持つことが必要だと思う。そして戦争抑止のための有力なファクターとして「経済発展」を挙げた筆者の主張には、大いに頷かされる。2018/02/08
Natsume
2
非常に平易な書き方で、特定のイデオロギーへの偏りなく、リベラリズムとリアリズムという国際関係分析の基本的なアプローチの概要を確認でき、この本が書かれた昨年よりさらにきな臭い現状を認識する視点を固められる。どうか戦争になりませんように、と祈るんじゃなくて、自分たちが意識してそうならないように行動しないといけないんだよな。2017/07/07