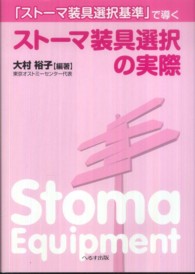- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
途上国ニッポンはなぜ一等国になれたのか? 「富国強兵」「公議輿論」――。幕末維新期、複数の国家目標を成就に導いた「柔構造」モデルとは何か? 政治史家と開発経済学者が明治維新の本質を捉え直す一冊。(講談社現代新書)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mitei
178
明治維新というのは1867年だけでなく大日本帝国憲法、国会開設の決まったところまでを明治維新としているのは新鮮だった。維新の志士が攘夷から開国倒幕へと一本道に変わっていくように見えるのはその時の最適解を求めてそれぞれの人が意見をすりあわせて行ったのだと感動した。2015/01/27
Rubik's
75
★★★★☆2019/09/09
ようはん
19
明治維新近辺の解像度が上がる一冊。幕末諸藩の内、明治維新の最大の立役者は薩摩藩という印象でその強みは西郷や大久保らの立ち位置や思考の異なる人物同士の連携はもとより、他藩内部の異なる派閥同士共巧みに連携できた柔軟性という点。2022/08/19
Nobu A
14
歴史は視点視座によって随分変わる。既読の「途上国のグローバリゼーション」の開発経済学者と政治史学者の学際的視点から明治維新を考察。明晰且つ斬新。「柔構造」と言う独自仮説を軸に3部構成。第一部は前後も含めた様々な動きを概観。情報過多で消化不足だが、その後改革諸藩比較、江戸社会の適応と段階的腹落ち。「後発国にとって国際統合とは、自国の歴史に恐らく一度しか訪れない、きわめて冒険的な過程」が心に響き、歴史を作った先人達が脳裏に浮かぶ。「翻訳的適応」等、適材適所的引用で秀逸に纏まった歴史本。やや難解だが面白かった。2020/07/19
樋口佳之
14
互いに矛盾を起こしかねない雑多な要素を平気で取り込み、目的に応じて適宜取り出すという芸当は、日本人に特徴的な性格であり、どこの社会でも見られるものではない。これをよくいえば柔軟性、包容力、プラグマティズムだが、逆に悪く評価すれば、原理の欠如、節操のなさ、雑種性ということになる。2017/03/05
-

- 電子書籍
- 異世界から聖女が来るようなので、邪魔者…
-

- 電子書籍
- HONKOWA 2023年7月号 HO…
-

- 電子書籍
- 蒸気原動機 機械系 大学講義シリーズ21
-
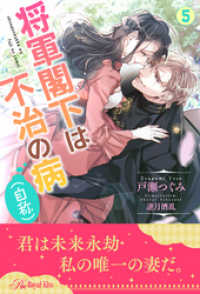
- 電子書籍
- 将軍閣下は不治の病(自称)【5】 ロイ…