- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
1945年8月15日、日本はポツダム宣言を受諾し、無条件降伏をした。ここに第二次世界大戦は終結。同月30日、連合国軍最高司令官ダグラス・マッカーサーは、コーンパイプを燻らせつつ厚木に降り立った。以来2000日におよぶ日本占領が始まったのである。その間、占領政策の下、昭和21年には日本国憲法が公布され、昭和23年には極東国際軍事裁判、いわゆる東京裁判の判決が下されるなど、激変する社会情勢のなか、「戦後の日本」がつくられていった。その立役者となったのは誰なのか。本書は、終戦から日本が自立復興の道を歩み出す、講和条約発効までを描いた、著者渾身の長編歴史評論である。陸奥宗光、小村寿太郎、幣原喜重郎等、卓越した外交官にスポットを当てながら、近現代の日本の歩みと外交史を事実に即して克明かつ冷静にたどった、著者のライフワーク「外交官とその時代」シリーズ5部作の掉尾を飾る、堂々の完結編である。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
読書ニスタ
36
楽観主義者、強運、主義主張がない、外交官でマッカーサーよりマッカーサー的、中位の人間。というのが、本書の吉田茂 評。戦後における重要な時期に、食料問題、農地改革、新憲法の公布、サンフランシスコ講和条約締結と、大きな仕事をまとめた男、吉田は、「強運」に尽きるのではないか。朝鮮戦争後の復興など、経済に集中できる基盤作りには間に合ったのだから。反面、マッカーサーの思惑通り動いたことが、日本人の自分たちで国の方針をまとめられない国体を作ったのかもしれない。チャーチルと似ているのはブルドッグ顔だけ?2019/09/16
James Hayashi
29
本文中にもあるが、吉田茂と言うよりマッカーサーとその時代を書かれている様。以前から疑問に思っていた、終戦後からの日本の親米感情について著者が述べる。終戦の翌年は台湾や満州からの供給が止まり、また国内の田畑も荒れ果て、平年以下の配給量であった。しかし吉田がマ元帥に頼み国民に小麦など供給された。その影には天皇の米国への問い掛けもあったという。その時点で米国への親しみが湧いたとのこと。悪の根源の様にみられる東条だが、東京裁判の発言を見るとやむを得なさとブレない透徹感が観れる。続く→2018/05/07
James Hayashi
25
終戦から吉田茂が日米安保を結ぶまでの占領時代。講和条約と日米安保という深い傷跡はさらなる長い歴史を経て評価されるべきなのかもしれない。戦略や外交など日本が欠落したものを今後どの様に養うのか?2020/05/04
ceskepivo
6
これは著者の至言である。ただし、昭和時代の国家運営には、長期的視点がもう少しあってもよかったのではないか。 「歴史というのは、その時々の人間と国家が生き抜いてきた努力の積み重ねであり、人間と国家の営みの大きな流れである。その大きな流れのなかで戦争も生じれば、平和も生じる。もともとその善悪を論じるべきものではない」2025/04/29
日の光と暁の藍
5
他のレビューにもあるが、『吉田茂とその時代』というタイトルではあるが、吉田茂の記述はあまりない。占領期がどのようなものだったのかを知るためには、手軽に読みやすい一冊だと思う。幣原喜重郎が、ただ一心に皇室制度を守るために動いていたこと、マッカーサーも皇室制度は守ろうとしたこと、 憲法よりも皇室制度の維持が日本にとってただ重要だったということはよく分かった。ただ、岡崎氏の、奥歯に物が挟まったような表現に本書の限界を感じた。令和の時代に読むべき本かと言われると、今この一冊を改めて読む価値はあまりないと思う。2024/06/23
-
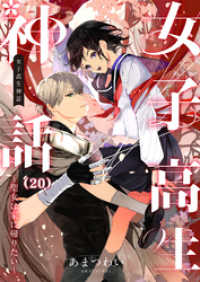
- 電子書籍
- 女子高生神話 ~聖女は家に帰りたい~ …
-
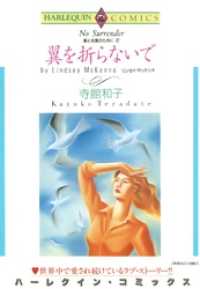
- 電子書籍
- 翼を折らないで【分冊】 2巻 ハーレク…
-
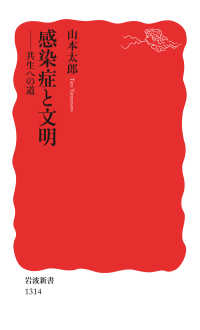
- 電子書籍
- 感染症と文明 共生への道 岩波新書
-
![劇画座招待席[23] 影狩り、其ノ三 小仏峠の虐殺](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-0706381.jpg)
- 電子書籍
- 劇画座招待席[23] 影狩り、其ノ三 …
-
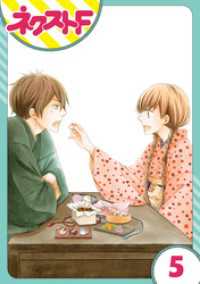
- 電子書籍
- 【単話売】印伝さんと縁結び 5話 ネク…




