内容説明
※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
私がこの本でもっとも述べたいことは,絶対音感があまり音楽的とはいえない能力だということである.それどころか,それはへたをすると音楽にとって好ましくないように働くことさえもあるというのが私の考えだ.(はじめにより)
優れた音楽家には不可欠の能力と思われがちな絶対音感.しかし,科学的な実験が示す事実は,そんなイメージとは反対のものだった.本書では絶対音感研究の第一人者が,データに基づき,現在までにわかっていることとそうでないことを明らかにする.さまざまな逸話や誤解,俗説を超え,絶対音感の真実をめぐる冒険.
目次
はじめに
第1章 絶対音感とは何か――絶対音感の概念をめぐる神話
「絶対音感」という言葉を吟味する――「絶対」神話と「完全」神話/絶対音感を定義する/絶対音感を測る際の問題/真性絶対音感と仮性絶対音感/反応の速さ/答の正確さ/絶対音感の下限/能動的絶対音感/絶対音感テスト/絶対音感を持つ人は耳がよいという神話/絶対音感がある人の聴覚世界――音がみなドレミに聞こえる?/潜在的絶対音感
第2章 音楽的ピッチ
物理現象としての音と聞こえとしての音/ピッチの性質/音階のピッチ/ピッチのふたつの側面――ピッチハイトとピッチクラス/ピッチらせん/絶対音高と相対音高/ピッチ輪郭と音程/音階と調性/和声感・調性感/なぜ相対音感があるのか
第3章 絶対音感の事実――実験から明らかになったこと
絶対音感の正確さとエラー・パターン/音色と音域による違い/ピッチクラスによる違い/反応の速さ/半音よりも小さなピッチの違い/ピッチ・カテゴリーの知覚/処理の自動化/ピッチと音高名の相互作用/ストループ効果/聴覚的ストループ効果/聴覚的逆ストループ効果
第4章 絶対音感を持つ人はどのくらいいるのか
稀少なものは価値がある/「一万人に一人」神話――バッチェムの研究/バッチェムの研究の問題点/「一五〇〇人に一人」神話/音楽家の中での絶対音感の割合/バッチェムの推定値/サージェントの推定値/遺伝学者の推定値/絶対音感は東アジア系に多い?/ドイチュの調査――絶対音感の声調言語起源神話/日本の音楽学生における絶対音感/絶対音感の国際比較
第5章 絶対音感は音楽をするうえで役に立つか――〈絶対音感=音楽的才能〉という神話
音楽的リテラシーの認知モデル/曲を聴いて楽譜に書くまでの過程/楽譜に書く/絶対音感は曲を楽譜に書くツールとして役に立つ/聴音テスト/聴音テストで何を見るのか――聴音テストの神話/聴音テストの妥当性/曲のイメージを楽譜にする/楽譜から音楽を読み取る/楽譜を見てすぐにメロディを正しく歌う――初見視唱/絶対音感を持つ音楽家が語ったこと
第6章 絶対音感を持つ音楽家――モーツァルトの絶対音感の神話
シャハトナーのヴァイオリンの神話/ヴァチカンのモーツァルト――「ミゼレーレ」の神話/幼いモーツァルトの絶対音感の神話
第7章 絶対音感を持つ人の相対音感
絶対音感は音楽的に価値があると言えるか?/音程識別の実験1/絶対音感を持つ人の相対音感はなぜ不正確だったか/音程識別の実験2/絶対音感保有者は音痴?/メロディを聴きくらべる/絶対音感保有者のメロディ識別能力/楽譜を見ながらメロディを聴く/絶対音感保有者の工夫/ポーランドの音楽学生に行った実験/相対音感の国際比較/日本の音楽学生はなぜ相対音感に弱いのか
第8章 絶対音感はどのように生じるのか――遺伝と経験をめぐる神話
遺伝と経験の役割/おとなは絶対音感を身につけることができるか/マイヤーの絶対音感訓練/いくらかの訓練効果はある/カッディの研究――訓練法の比較/ブレイディの挑戦――唯一の成功例?/絶対音感教材「バージ法」――本当に効果があるか/プラセボ効果/おとなは絶対音感を獲得できない/こどもは絶対音感を獲得できるか/初期学習説/ヤマハ音楽教室の絶対音感訓練/こどもたちの絶対音感獲得過程/結論に飛びつく前に……/ヤマハの音楽教育システム/江口式絶対音感プログラム/臨界期とは何か/絶対音感の臨界期仮説 /絶対音感が学習できなくなるのはなぜか/絶対音感の遺伝的背景――家族を調べる/双生児を調べる/絶対音感遺伝子はあるか/絶対音感が進化する理由があるか
巻末註
目次
はじめに
第1章 絶対音感とは何か――絶対音感の概念をめぐる神話
「絶対音感」という言葉を吟味する――「絶対」神話と「完全」神話/絶対音感を定義する/絶対音感を測る際の問題/真性絶対音感と仮性絶対音感/反応の速さ/答の正確さ/絶対音感の下限/能動的絶対音感/絶対音感テスト/絶対音感を持つ人は耳がよいという神話/絶対音感がある人の聴覚世界――音がみなドレミに聞こえる?/潜在的絶対音感
第2章 音楽的ピッチ
物理現象としての音と聞こえとしての音/ピッチの性質/音階のピッチ/ピッチのふたつの側面――ピッチハイトとピッチクラス/ピッチらせん/絶対音高と相対音高/ピッチ輪郭と音程/音階と調性/和声感・調性感/なぜ相対音感があるのか
第3章 絶対音感の事実――実験から明らかになったこと
絶対音感の正確さとエラー・パターン/音色と音域による違い/ピッチクラスによる違い/反応の速さ/半音よりも小さなピッチの違い/ピッチ・カテゴリーの知覚/処理の自動化/ピッチと音高名の相互作用/ストループ効果/聴覚的ストループ効果/聴覚的逆ストループ効果
第4章 絶対音感を持つ人はどのくらいいるのか
稀少なものは価値がある/「一万人に一人」神話――バッチェムの研究/バッチェムの研究の問題点/「一五〇〇人に一人」神話/音楽家の中での絶対音感の割合/バッチェムの推定値/サージェントの推定値/遺伝学者の推定値/絶対音感は東アジア系に多い?/ドイチュの調査――絶対音感の声調言語起源神話/日本の音楽学生における絶対音感/絶対音感の国際比較
第5章 絶対音感は音楽をするうえで役に立つか――〈絶対音感=音楽的才能〉という神話
音楽的リテラシーの認知モデル/曲を聴いて楽譜に書くまでの過程/楽譜に書く/絶対音感は曲を楽譜に書くツールとして役に立つ/聴音テスト/聴音テストで何を見るのか――聴音テストの神話/聴音テストの妥当性/曲のイメージを楽譜にする/楽譜から音楽を読み取る/楽譜を見てすぐにメロディを正しく歌う――初見視唱/絶対音感を持つ音楽家が語ったこと
第6章 絶対音感を持つ音楽家――モーツァルトの絶対音感の神話
シャハトナーのヴァイオリンの神話/ヴァチカンのモーツァルト――「ミゼレーレ」の神話/幼いモーツァルトの絶対音感の神話
第7章 絶対音感を持つ人の相対音感
絶対音感は音楽的に価値があると言えるか?/音程識別の実験1/絶対音感を持つ人の相対音感はなぜ不正確だったか/音程識別の実験2/絶対音感保有者は音痴?/メロディを聴きくらべる/絶対音感保有者のメロディ識別能力/楽譜を見ながらメロディを聴く/絶対音感保有者の工夫/ポーランドの音楽学生に行った実験/相対音感の国際比較/日本の音楽学生はなぜ相対音感に弱いのか
第8章 絶対音感はどのように生じるのか――遺伝と経験をめぐる神話
遺伝と経験の役割/おとなは絶対音感を身につけることができるか/マイヤーの絶対音感訓練/いくらかの訓練効果はある/カッディの研究――訓練法の比較/ブレイディの挑戦――唯一の成功例?/絶対音感教材「バージ法」――本当に効果があるか/プラセボ効果/おとなは絶対音感を獲得できない/こどもは絶対音感を獲得できるか/初期学習説/ヤマハ音楽教室の絶対音感訓練/こどもたちの絶対音感獲得過程/結論に飛びつく前に……/ヤマハの音楽教育システム/江口式絶対音感プログラム/臨界期とは何か/絶対音感の臨界期仮説 /絶対音感が学習できなくなるのはなぜか/絶対音感の遺伝的背景――家族を調べる/双生児を調べる/絶対音感遺伝子はあるか/絶対音感が進化する理由があるか
巻末註
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
Tadashi_N
mit
tom
MASA123
塩崎ツトム
-

- 電子書籍
- 傷だらけの公爵令嬢は、隣国の皇太子に溺…
-

- 電子書籍
- ドラコラン【タテヨミ】第86話 pic…
-

- 電子書籍
- 僕と君の大切な話(4)
-
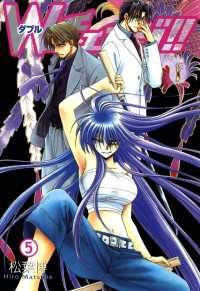
- 電子書籍
- Wチェンジ!!(5) 月刊コミックブレ…
-
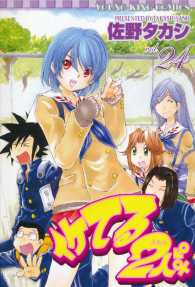
- 電子書籍
- イケてる2人 (24)




