内容説明
「浅草」から「銀座」へ、「新宿」から「渋谷」へ――人々がドラマを織りなす劇場としての盛り場を活写。盛り場を「出来事」として捉える独自の手法によって、都市論の可能性を押し広げた新しき古典。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
zirou1984
28
冒頭部分とかすごい退屈で冗長な感じでこれ学生レベルの文章じゃ…と思ったら著者の修士論文を加筆したもので本当に学生レベルだった。とはいえ、後半の実証部分はは興味深い内容が多く、明治期の浅草―銀座の発展についての具体的事例というのはここまで実感のある論述に初めて触れることが出来て新鮮であった。対比的に示される昭和期の新宿―渋谷の発展模様についても、猥雑さから生まれた新宿と演出の場として作られた渋谷のそれぞれが浅草―銀座と照応しているというのも面白い。3章以降からいきなり読んだ方が楽しめる。2017/02/18
あかつや
11
都市論の白眉。ものすごく面白かった。盛り場を単なる空間としてではなく、人間と空間が相互作用することで現れる出来事として捉え、その手法で各年代ごとに分析している。なんていうか、都市の文脈を読むって感じだろうか。80年代に書かれたものだそうだけど、今の世にあっても全然古びてないなあ。それどころかこれは現実の盛り場だけじゃなく、現代のインターネット上の「盛り場」についても当てはまるんじゃないかと思える。こちらの場合は物理的な制約がない分盛衰のサイクルがはやく、出来事の流れを実感として捉えやすいかもしれない。2020/09/10
Shin
11
著者本人もあとがきで書かれている通り、若さゆえの論理展開の回りくどさで必ずしも読みやすくはないが、都市を「盛り場」という現象で捉え、それをさらに「演劇」とのアナロジーで読み解こうとする視座は、都市論の枠に留まらない独創的かつ刺激的な方法論を与えてくれる。アカデミズム以外のより実践的な、例えばマーケティングの分野でも幅広く適用できるのではなかろうか。難しいことを抜きにしても、明治から戦後にかけての東京各所の変遷を「街並み」と「人びと」の両方から描写していくダイナミズムは、知的醍醐味を与えてくれる。2011/11/04
キョートマン
8
こんな読み応えのある文章を修士で書いていたのは恐ろしいな2021/08/30
Hiromu Yamazaki
7
1年半ぶりに再読。近年世に出回る都市論は全てこの本に強い影響を受けていると言っていい。活動する人間の振る舞いと、それを支える構造的機制の二方面から盛り場を照らすその手法は、対象と時代は違えども現代の都市、社会を考察する上でも十分通用するはずである。著者本人があとがきで述べているように若干前のめりな論の展開も多少見られるが、それでも修士論文でこのクオリティは脱帽するしかない。2014/01/19
-
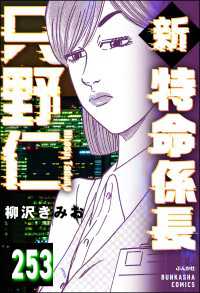
- 電子書籍
- 新特命係長 只野仁(分冊版) 【第25…
-

- 電子書籍
- カップルゲーム 第2話(1) サイコワ…
-

- 電子書籍
- 攻撃力極振りの最強魔術師~筋力値999…
-

- 電子書籍
- プリンスの罪な誘惑【分冊】 6巻 ハー…





