内容説明
自民党憲法草案ならますます日本は衰退する。
衆参両院で「改憲勢力3分の2以上」が現実となった今、安倍自民党政権は、憲法改正に向けて一歩一歩「前へ」と突き進んでいる。
今の改憲論議では、戦争の放棄を謳う「第9条」や、災害・テロ対策のための「緊急事態条項」などが俎上に載せられている。しかし、それらの議論は、いわば安倍政権と“同じ土俵”で戦おうとすることであり、最後は“力比べ”となってしまう。そうではなく、首相の改憲提案を逆手にとって、憲法で規定された統治機構を改めることこそ「一強」体制を断ち切る効果的な攻め手となる――この全く新しい改憲論のカギとなるのが憲法第8章だ。
同章は「地方自治」を謳いながら、結局は中央政府がすべての権限を握り、中央の意向に従う者だけに目こぼしする歪な政治の論拠となっている。しかも、自民党の憲法改正草案はそれをさらに強化するものであり、ますます日本を衰退させてしまうと著者は警鐘を鳴らす。
繁栄の単位としての道州制の導入、生活圏としてのコミュニティの構築など、地方の「自立」を促す憲法を作れ――。「平成維新」の提唱者・大前研一氏が、旧態依然とした「安倍一強」中央集権体制に引導を渡す、初めての本格的改憲論。
【ご注意】※お使いの端末によっては、一部読みづらい場合がございます。お手持ちの端末で立ち読みファイルをご確認いただくことをお勧めします。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
HMax
26
もう30年以上前に書かれた、大前版の新日本国憲法。改憲や加憲ではなく「創憲」。古くなった単発エンジンをアベノミクスでいくら吹かしても墜落するのは目に見えている。日本を復活させるには道州制による複数エンジンを持った日本へ根本的に変えなければならない。「改憲=改悪=戦争」という条件反射がマスコミ、日教組によって植え付けられているので、9条ではなく第八章からお試しで改憲してみては?そんなせこいことを言わずに、大前さん、令和維新の会を作りますか。2020/07/13
ちさと
25
憲法第8章の定めにより、日本の地方は単に国から業務を委託された出先機関でしかない。地方衰退の原因は憲法にあるとして、「分権」ではなく経済的に自立した「地方自治」へと移行できるよう、憲法草案を提示しています。事実8章は他の章に比べると、なんだかささーっと創られたようにも見えます。政府の見える手が無くなったら、今度は地方の小さな政府が同じように、集権システムを作る気もしますけどね…。2018/09/20
あんさん
16
政治家の減税案競争に触れ、有権者がさもしいんだと検索してヒットした本。内容は大前流の、特に第8章地方自治をキーにした改憲論。道州制導入によりドイツ、イタリアあるいはスイス的に各地で特徴的産品を発展させる提案はなるほどと思った。スタッフトレーニングで使ったという各国憲法を読んでみたい。マスコミも与党案を流すだけでは役割を果たしていないだろう。「誰が払う財源でこれをやるのかという説明もないまま、恩恵を享受することだけを謳って得点を稼ごうとするレベルの低い政治家を、レベルの低い国民が受け容れてしまっている」2025/06/01
りょうみや
14
こんなマニアックなタイトル付けるよりも素直に道州制のタイトルの方がよいと思える。アベノミクスの失敗から道州制・地方自治の話題、改憲論へと流れていく。ドイツ、イタリアの例から見る地方自治の必要性、特に同じ敗戦からスタートしたのに今の日本との差が生じた原因の考察がおもしろい。著者の主張の通りに日本が変われば良くなるとは思えるが、あまり現実性が感じられない。例えば公務員、教師を何割削減とか言っても、そのクビを切られた人の生活など途中過程や弊害などがすっぽ抜けているように見える。2016/10/07
まゆまゆ
8
地方自治について書かれている憲法92~95条は、明治憲法以来の中央集権体制から変わっていない。自立とコミュニティこそ地方自治の根本のはずだが、その定義も憲法にはない。国による法律の範囲内でしか行動できない地方はまさに地方公共団体である。28年前に書かれた筆者の憲法草案から現状認識が変わっていないことこそ日本が成長できていない証拠……そういえば最近はめっきり道州制という言葉を聞かなくなったなぁ……2017/01/31
-

- 電子書籍
- 制限△解除 何歳からでも思い通りに生き…
-
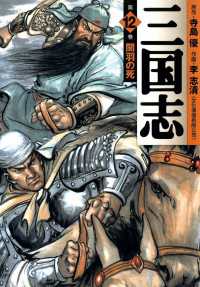
- 電子書籍
- 三国志 12 MFコミックス フラッパ…
-
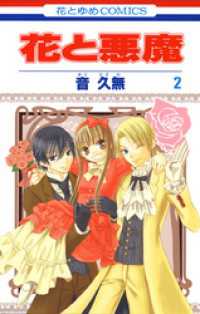
- 電子書籍
- 花と悪魔 2巻 花とゆめコミックス
-
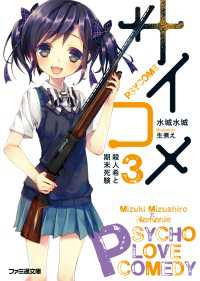
- 電子書籍
- サイコメ 3 殺人希と期末死験 ファミ…





