内容説明
「人間の一生は、一回かぎりのものである。その一生を『想像力』にぶちこめたら、こんな幸福な生き方はない。絵とは人生そのものなのだ」――絵を前にした人へ、著者自ら原点に立ち戻り綴った名エッセイ。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ホークス
32
1976年刊の美術評論と講演。見た人を変えてしまうほどの絵を著者は求めており、岡本太郎と似た熱気が感じられる。のめり込む様に絵を観察し、画家の思考を推理する。時代遅れで偏屈だが面白かった。「絵は感覚的な言語」だから具象画も抽象画も同じという話は理解半分だが感心した。ドイツリアリズムの章が興味深かった。厳しさと真面目さに加え、哀しいユーモアが漂う世界。背景の階級社会も考察している。階級意識や差別意識は人の業病だという事は確かだ。最後の「ゴッホの遺書」は難解だったが、やはり「星月夜」は素晴らしい。2019/01/23
スイ
18
絵画批評、特にゴッホについて。 日本の美術界に対しては辛辣で、呑気な鑑賞者である私もビクッとしたが、絵画を読む、ということについては感覚で少しだけわかる気がする。2025/03/03
kana0202
3
良い意味でも悪い意味でも小林秀雄の影響の大きさを感じる。大事なのは、感覚だといいきられてもなぁ、と思わざるを得ない。しかしところどころ鋭いと思わせられるところもあって、読む価値ないとは思わないけれど、用心しながら読む必要があるだろう。しっかりと分析的に、それこそもっと本気で読んでから、感覚や想像力という語彙にたどり着くべきだ。時代的な制約はあるにせよ、小林流の文章は批評ではなく感想なのであって、現在ではもうこういうのはよくない。これはけっして絵画論などではない。絵画についての彼の意見である。2023/02/12
樹木
3
ゴッホ展を見て、彼の描く自然と色彩の力強さにひかれ、改めて読み直した。絵とは想像力であり、個性であり、感覚であるという。世界の中に、自分が感じ、つかみとったもうひとつの世界を表現するのが、絵であり、芸術と筆者はいう。そうした自己表現の結晶だからこそ、絵は「読まれる」のだ。そして、自己表現の代表的画家として、ゴッホが挙げられる。展覧会で初めて彼が37で亡くなり、創作活動がおよそ10年だったことに驚いた。彼の作品群が私たちの眼をつかむのは彼の短くて太い人生の表現がそこに詰まっているからだと感じた。2018/01/02
ぱぴ
2
読んでいて苦しかった。でも、今の自分で読むことが出来て本当に良かった。絵というものを真に理解するためには、美しいものばかり追い求めて満足するのではなく、「読んで」、「見て」、「感じる」こと。その為には個人の感覚をもっと研ぎ澄ませることが必要。豊かさだけでは決して得ることが出来ない体験が、人間を高次の段階へ高めていく。ゴッホという芸術家を狂人だったで片付けては決していけない。彼の絵から漲る生命力を、正面から受け止められる人間になりたいと思った。読む度にまた違った発見が出来そうなので、時々読み返していきたい。2019/07/28
-
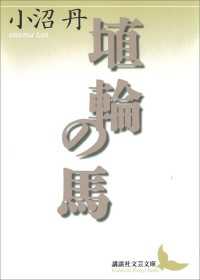
- 電子書籍
- 埴輪の馬 講談社文芸文庫








