内容説明
近代国際法の元となったのは、三十年戦争の講和条約、ヴェストファーレン条約。これにより「ヨーロッパにおける秩序」が形成された。それ以降、大きな戦争が起きるたびに、「地域における秩序」が確立されてきた。現在の「真にグローバル化した」国際環境では、どのような「国際秩序」が作られるべきなのか--いま最もホットな話題に、キッシンジャーが挑んだ話題作!
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
143
キッシンジャーの何年か前に出版した「外交(上下)」を補うものとして出版されたような気がします。最近の状況まで書かれていていいのですが書かれている方もいるとおりなんとも訳がこなれていなくて読みづらい感じがしました。きちんとした定訳がある言葉もご自分の言葉で訳している感じです。日経から改訂版を出してもらいたい気もするのですが、私は原書を購入して読み直そうかと思っています。2016/11/15
やいっち
55
ハアハアゼエゼエ辛うじて通読。この手の本は、斜め読みで済ませる(というか初めから相手にしない)。何故なら大概の政治本は数年も経ないうちに内容が陳腐化するから。同僚に頂いた本。なので敢えて読み出した。が、甘かった。原書の刊行は2016年なので、データや世界の情勢は10年前(書かれたのは2014年)。それでも読み応えがあった。さすがにキッシンジャーだけのことはある。仕事の車中での待機中に慌ただしく読む本じゃなかった。2025/02/24
Rie【顔姫 ξ(✿ ❛‿❛)ξ】
32
比較的新しい本だったので、現在の国際秩序について書かれているのかと思ったら、その根底にある歴史の本でした。全部読み切れてないけど、一応登録。グローバリゼーション、インターネットの普及が国際秩序にどのような影響を及ぼすのか、という点についてもう少し掘り下げた著者の本があれば読んでみたい。2017/09/24
Shin
22
主に宗教戦争以降の世界史を、「国際秩序」という補助線を引きながら概括し、秩序をもたらし、また破壊する歴史的動因を俯瞰的に分析する。軸となるのは欧州の戦塵の中で生まれたヴェストファーレン・システムであり、力のバランスによって突出した国を作らないことを各国は目指してきたが、その当たり前と思える価値観は、様々な国が持つ〈秩序観〉のひとつに過ぎないことが示される。国際関係はとかく「国益」の相互衝突と捉えられがちだが、もうひとつメタレベルに「秩序の定義」の違いがあり、その相克によって諸々の混乱が生じるのだと分かる。2020/06/07
Hidetada Harada
21
先に読んだ佐藤優さんの本で、キッシンジャーのことがちょこっとだけ書かれていて、この人に興味を持ったのが読み始めたきっかけでした。大いに苦戦して3週間掛けてなんとか読了。印象に残ったのは宗教に関する考察と、テクノロジーに書かれた章。勉強になりました。それにしても、思考の深さと分析力、そして目的意識の高さは尋常ではないです。時間を置いてまた読みたいと思いました。2017/12/03
-
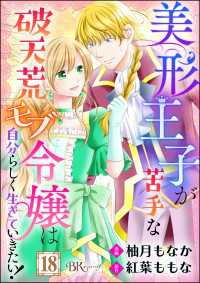
- 電子書籍
- 美形王子が苦手な破天荒モブ令嬢は自分ら…
-

- 電子書籍
- Berry's Fantasy メイド…
-

- 電子書籍
- 土砂降り令嬢の傷心旅行 ZERO-SU…
-
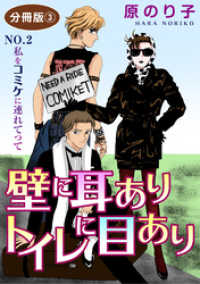
- 電子書籍
- 壁に耳ありトイレに目あり NO.2 私…
-

- 電子書籍
- うちの会社の小さい先輩の話 ストーリア…




