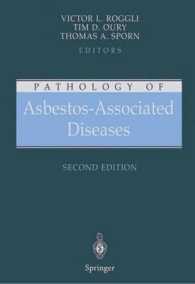- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
倫理学とは「倫理について批判的に考える」学問である。すなわち、よりよく生きるために、社会の常識やルールをきちんと考えなおすための技術である。本書では、「功利主義」という理論についてよく考えることで、倫理学を学ぶことの意義と、その使い方を示す。「ルールはどこまで尊重すべきか」や「公共性と自由のあり方」という問いから「幸福とは何か」「理性と感情の関係」まで、自分で考える人の書。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ころこ
41
倫理の規則をメタ的に重ねていくと、いつか功利主義になります。しかし、それは何もいっていないに等しい。なぜならば、何に価値を置くかによって、効用は大きく異なるからです。功利主義によって、相対化された中でも薄ぼんやりと答えがみえると錯覚させるのであれば、本書は無意味でしょう。功利主義が主義だと思えるのは、その人の思考の幅が狭いからです。他方で、功利主義を原理だと思うのは間違いだと、気付くきっかけとなるのであれば読む価値はあります。公共政策のようなことを考えるのであっても、読者が少し躓くようにできています。2019/08/27
mana
35
新書として、軽く功利主義や倫理学に触れられる本。様々な立場の功利主義について紹介されており、入門に持ってこい。2023/03/08
テツ
24
功利主義が導き教える「最大多数の最大幸福」 それについて自分なりに考えるのは幸福や正義、最大多数とはなんぞやということについて自分だけの思考を創り上げていくことだ。倫理学的な思考の形。既存の価値観を疑いながらも、それを破壊して新しい何かを創り上げるためには緻密にロジックを積み重ねていかなければならないと知ること。感情の赴くままにがなりたてることが是とされる空気が熟成されているような気がする昨今だけれど(特に正義を背負うとね)本来はこうして自分の中で血を吐くまで思考を重ねるべきだ。外部に出すのはその後だ。2019/12/06
きいち
24
国境の話でもいじめの話でも年金の話でも、合意形成の難度が上がっている中、功利主義は今とても威力を発揮する考え方なのでは?と感覚的に思ってきた。非常にわかりやすく実感的に解説してくれるこの本は、その感覚をしっかりと根拠づけてくれる。もちろん、「すべて損得づくで早く正しく決めれるから」というのではなく、お互いがベースにしている「損得の尺度」のズレを意識することで、対話や議論での「かみ合わなさ」が少しずつ解消していくから。商売の場面でも同じだが、「話なんかしたってしかたない」という態度こそ、一番の敵なのだもの。2013/09/11
あなほりふくろう
23
倫理、でなく倫理学。功利主義をテーマに、倫理に対する批判的思考をしていく(これが大事!)入門書として、これは良い一冊。先人達によるアップデートの変遷とともにホリエモンや菅直人、ホテル・ルワンダなども俎上にのるなど、取りつきやすいケーススタディを通して批判的思考を学んでいく。よくかみ砕いてあると思う。2020/05/31
-
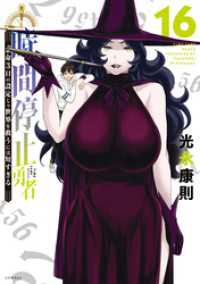
- 電子書籍
- 時間停止勇者(16)
-
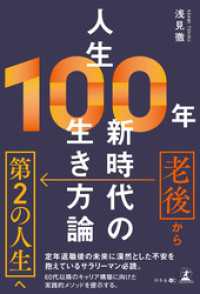
- 電子書籍
- 人生100年 新時代の生き方論