内容説明
近年,人々や社会,国家のアイデンティティの根幹に関わる,一人一人の文化的リテラシーを問われる場面が多くなっている.固有の文化とは何なのか? 守るべき文化とは? あるいは文化を政策に活用することの是非は? 国内外の最新の動向を紹介し,観念論と政策論の双方の視点から,文化の新しい使い方,その危険性と可能性を考察する.
目次
目 次
はしがき──「文化」は、いま
第一章 グローバリゼーションは「文化」を殺す?
1 スーパーモダン
2 ポストモダン
3 肯定派と否定派
4 保守派とリベラル派内部の不協和音
5 ナショナルな次元の重要性
6 重層的なガバナンス
7 グローカリゼーション
スローフード/創作エイサー/先住民族
8 搾取される「伝統文化」
9 ハイリスク・ハイリターンの皮肉
10 「われわれはみんなペストの中にいるのだ」
第二章 台頭する「人間の安全保障」という視点
1 格差の再編成
2 新自由主義の論理と力学
オーディット文化/消費者至上主義/市場化される精神性と身体性/ 〈帝国〉の権力とネットワーク
3 「人間の安全保障」
4 セーフティーネットとしての文化
5 教育の挑戦
6 製品の可能性
7 言語という権利
8 方便としての文化
9 文化相対主義の陥穽
第三章 ソフトパワーをめぐる競合
1 ソフトパワーをめぐる狂想曲
文化の地政学/ソフトパワーとしての「人間の安全保障」
2 パブリック・ディプロマシーの時代
3 「対外発信強化」の陥穽
4 道義的な高潔さ
5 「支配」から「支援」へ
6 グローバル・シビリアン・パワー
第四章 新しい担い手たち
1 政策的価値は「不純」か?
2 ガバナンスの新たな潮流
3 米国モデルの優位性
4 創発的な試み
5 日本が直面する課題
評価や測定は可能か
第五章 理論と政策の狭間で
1 「離見の見」
2 構築主義
3 境界線への眼差し
4 境界線を編み直す
芸術という試み/市場という試み/政治という試み/外交という試み/リベラル・アーツという試み/文化人類学という試み
5 「文化」を語れなくなった時代
6 一九九〇年代の米国の経験
7 新たな問い
おわりに──「文化」の未来
あとがき──ピーボディ四六号室
-
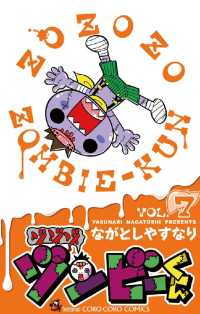
- 電子書籍
- ゾゾゾ ゾンビーくん(7) てんとう虫…
-

- 電子書籍
- 龍-RON-(ロン)(25) ビッグコ…



