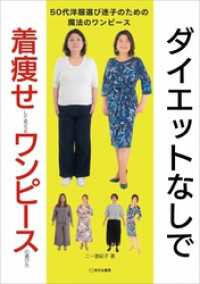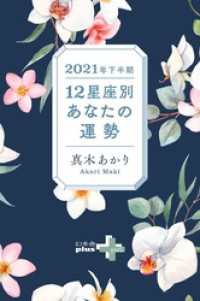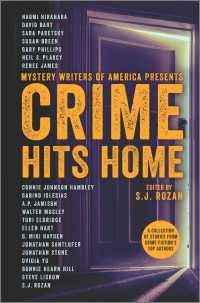内容説明
精神障害やアルコール依存などを抱える人びとが、北海道浦河の地に共同住居と作業所〈べてるの家〉を営んで30年。べてるの家のベースにあるのは「苦労を取りもどす」こと――保護され代弁される存在としてしか生きることを許されなかった患者としての生を抜けだして、一人ひとりの悩みを、自らの抱える生きづらさを、苦労を語ることばを取りもどしていくこと。
べてるの家を世に知らしめるきっかけとなった『悩む力』から8年。 浦河の仲間のなかに身をおき、数かぎりなく重ねられてきた問いかけと答えの中から生まれたドキュメント。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
寛生
58
【図書館】息を呑むような美しさで本書が終わる。読みながら、何度も、もしフコーがこの本を読んだらーと思う。フランスの精神分析家達も喜んでこの本を読むはず。かなり貴重なアーカイブだと思う。現代精神医学がいとも簡単に〈痛みと苦しみ〉を投薬によって解決しようとする姿勢に真っ向から対抗していくような投げかけがある。ここに〈生死〉を超える価値のようなものがあり、血みどろの精神的重荷を生きていく人間同士が〈何か〉を積み重ねていく軌跡をみる。それは「身体性が担保する不条理」だろうが、フコーにいわせればそれは「真理」だ。2014/04/08
こばまり
57
悩み苦しんで、社会と繋がってそして死んでいく。それこそが生の醍醐味であると説く。ラジオ番組のアーカイブか、武田鉄矢氏の熱い書評を耳にしたのがきっかけ。さもなくば、べてるの家は精神障害者のユートピアであるとの浅い認識のままだったろう。金八先生ありがとうございました。2018/12/16
あかは
50
まずタイトルにひかれた。え?なんで?って。べてるの家のことはどこかできいたことはあるけど、よくは知らなかった。主に出てくるのは統合失調症のひとたち。彼、彼女らが、自分を研究しどういうときにこうなるのか、皆でミーティングを重ねていく。もちろん病院にも行くが医師は治さない、コントロールするだけだといって最低限の薬しか出さない。 皆、病気をもっているのに、なぜか和やかな空気が流れていたりする。同じ人達の共同生活だからだろうか。でも、そう見えても誰もが、苦しんでいる。苦しみながら生きている。すさまじい事件も2016/11/05
おたま
41
著者が10年近くに渡って浦河べてるの家で、スタッフや当事者に行ったインタビュー、それに当事者研究や講演会、ミーティングでの話等の記録であり、そこから考えたことをまとめていったもの。書名の『治りませんように』は、病気が治ると、朝7時に起きて出社とかしなくてはならない、そりゃ大変だよ、「治りませんように」という当事者の語りから来ているらしい。これはなかなかに奥深い言葉。自分は健常者として生きられないという悲しみでもあり、なおかつ病気でよかったという安心感も感じられる。⇒2023/04/23
きいち
28
接客の場なり職場なりで精神に何らかの障害を持つ人と実際に接する時、その内側まで考えを到らせる余裕は、正直自分には無い。無駄な先入見から身を離し、目の前で起こっていることをできる限りまっすぐ受け止めることで精一杯…。だからこの本が医師やPSW(本当に尊敬する)の側ではなく、病を丁寧に生きている人たちの側から書き進めてくれていて、自分と地続きの存在であると感じられたことは、とても素敵な体験だった。◇当事者として生きようとする意志、そのものが目的である対話、どれも、僕らにとっての「最前線」。前衛としてのべてる。2013/08/04