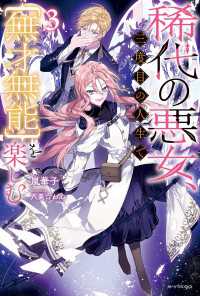内容説明
人間には見えない色が見える「チョウ」や「鳥」、夜目が利く「ネコ」、速く動くものは見えない「カタツムリ」など、同じモノを見ていても見え方が違う生き物たち。そんな彼らの「見えている世界」を通じて、この世の中がいかに多様な世界で満ちているか、私たち人間はその“ほんの一部”しか見えていないかを教えてくれる、読むほどにワクワクする科学エンターテイメント!
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ホークス
41
2012年刊。視覚を中心に、感覚器官の進化や機能、生態との関係を分かりやすく解説する。光を見分ける細胞は、人間の場合3種だがアゲハ蝶は5種。「光の三原色」は人の話で、アゲハが見ている「五原色」の世界を我々は感じられず、表現もできない。想像すると眠れなくなりそう。コウモリなら音で、カタツムリなら触覚で、ミミズは皮膚下の様々な細胞で外界を「見る」。彼らがどう感じて、どんな心の世界を描いているかは永遠の謎。人間も一人ずつ、器質的に違う。発達の仕方も環境も様々。世界の感じ方が色々なのは、豊かな事だと思う。2022/06/12
イリエ
7
もっと豊富なグラビアや空想図を期待して手にしたのですが、へぇ~まあそうだよなぁといった程度の新書でした。ただ、「ミミズのあなふさぎ」行動は面白かった。目がないのに、皮膚感覚だけで世界を観ているミミズ。モグラにも不思議な興味がわきました。2016/07/22
メイロング
3
生き物の視覚だけで一冊できるものなんだなー。でも今、まさに調べたいことのど真ん中でありがたい。初めは昆虫の話なのに、ラストは心理学社会学的な分野にシフトしていく。可視光線のグラデーションみたいだね。2017/11/07
daimonn
3
それぞれ見ている世界もその見方も違うけど、生き延びるため、生きていくのに都合のよいように進化してきた生き物たち。ヒトも昆虫も鳥も植物も、あらゆる生き物の現在の姿、形態がそれぞれの最新モデルと考えると、とても興味深い。はじまりは偶然に偶然が重なってうまれた小さな細胞だったのものが、ここまで多様な生物にまで進化するなんて奇跡だな…。そして花をカラフルにしてくれた昆虫にはありがとうと言いたい。2012/03/24
Fujikawa Yoshikazu
3
この世界に色や音楽はない。色や音楽は物理的性質を検知し価値観というフィルターを通して総括しただけのもの。つまり受け取る側の主観である。逆に言えば、心の豊かさが世界の見え方を変える。だから心を磨く必要があるのでしょう。2012/03/17