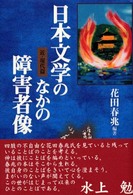内容説明
戦乱の中世、武士は熱心に和歌を詠み続けた。武家政権の発祥地・関東を中心に、鎌倉将軍宗尊親王、室町将軍足利尊氏、江戸城を築いた太田道潅、今川・武田・北条の戦国大名三強を取り上げ、文学伝統の足跡をたどる。
【目次】
序章 源氏将軍と和歌
第一章 歌人将軍の統治の夢―宗尊親王と鎌倉歌壇
第二章 乱世の和歌と信仰―足利尊氏と南北朝動乱
第三章 武蔵野の城館と歌人―太田道灌と国人領主
第四章 流浪の歌道師範―冷泉為和の見た戦国大名
終章
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
軍縮地球市民shinshin
16
武士はなぜ歌を詠むのか、の答えはやはり政治的なものであったと言える。地方に割拠する戦国大名が朝廷に取り入るためには公家と付き合う必要があり、そのてために和歌、連歌の能力は必須であったからである。本書はそれだけではなく、地方にあって都への憧れ、地方でも一目置かれる勢力になるためには、歌でも詠んで文化サロンでも設えないと、国人たちに示しがつかなかったという。その割には京風の文化人かと思っていた今川義元も和歌の才能はそれほどでもなかったらしい。国文学者の本だが日本史学の近年の研究成果も巧みに取り組んでいて面白い2018/09/28
ほうすう
13
和歌というと雅なものかと思っていたが、中世武士の世ともなるとずいぶん政治的で生臭くなるものだと感じた。4章立てで宗尊親王・足利尊氏・太田道灌・冷泉為和の四名を主として取り上げて時代の変遷とともに和歌のありようの変化も描かれている。一番興味深かったのは歌道師範でありながら今川家中において一門に準ずる扱いを受けるまでの力を持った為和の話であろうか。興味深い内容ながらどうにも読みづらさも感じた本であった。2019/11/11
Toska
9
中世武士というと仁義なき狂戦士的なイメージの強い昨今だが、それだけじゃないよね、という話。強いだけでは駄目で、最低限の文化的素養がなければ通用しない。また、和歌は優れたコミュニケーションツールであり、人と人、あるいは人と神仏を結びつける重要な役割を果たしていた。戦国期にあっても歌道など文化面での師範として武士たちを拝跪させた公家衆は、ソフトパワーの何たるかを知り尽くしていたのだろう。成り上がりの人間が却って既存秩序に権威の拠り所を求めるという図式は、黒田基樹氏の『下剋上』にも通じるものを感じた。2021/07/27
しずかな午後
8
名著。読後は感動的ですらあった。鎌倉時代から戦国までの中世の歴史全体を視野に入れながら、時代の変化のなかで和歌という文芸がどのような意味を持っていたのか、列伝体によって描きだす。中心になるのは、宗尊親王・足利尊氏・太田道灌・冷泉為和、それぞれ鎌倉・南北朝・室町・戦国に当たる。読んでいて分かったのは、武士にとって和歌は単なる文芸という以上に、朝廷の権威につながる手段であり、歌会・師弟関係などの人的ネットワークの構築が重要な意味を持っていたということだ。2023/07/13
mk
7
鎌倉期の宗尊親王(公家)、南北朝期の足利尊氏(武家)、室町末期の太田道灌(武家)、そして戦国期の冷泉為和(公家)と、各時代の東西歌壇を象徴する人物を狂言回しにして、広がりゆく詠み手の裾野にも目配りする考証は、まさしく当代随一の中世文学研究者のもの。歌壇の隆盛と安定は内政の安定(詠歌を支える社会的条件)に直結するという一貫した視野のもと、中世武家社会と和歌師範の営為との関係を語り直した本書の功績は大きいと思う。歴史学と中世文学の最先端の成果が随所に参照されている点も和歌文学研究の広がりを感じさせる。 2017/03/08