- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
学校をより良くするためには、まず何よりも教師を変えなければいけない。馴れ合いの教育現場のなかには、ダメな教師や困った校長がまだまだ存在する。同時に、能力が高い教師は正しく評価されてはいない。それは、教育というサービスを受ける児童生徒と保護者をないがしろにしてきたからだ。今必要なのは学習者による評価制度だ。評価制度の具体例を提示しながら、その可能性に迫っていく。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
T-山岡
3
「学校や教育委員会の馴れ合い体質を排除し、公立校の教員が適切な外部評価の中で実力を醸成できる制度を確立すべき」という主張自体には首肯できる。ただ、その主張のための引用や例示が多分に三文記事的で、説得力を欠いているように感じた。また、著者は保護者や学習者の声を性善説的に捉え、あたかもモンスターペアレンツなど存在しないかのように述べるが、現実にはどう転んでも擁護できないノイジー・マイノリティも発生している訳で、外部評価の導入に際しては、そのような声に踊らされない体制も同時に確立しなくてはならないだろう。2010/10/27
すたれびと
2
著者の前書『ダメな教師の見分け方』が面白いと思い、実家に置いてあったので読んでみた。教育に関する様々な事例を通して、著者の個人的考察を述べていくスタイルが取られている。学校をいかに良くしていくかを考える上で教師を目指したり、子供を持つ親は一読してみるといいかもしれない。「責任の所在」に関しては概ね考えが一緒であった。著者の教師時代のエピソードをもっと収録したり、対談を引用したりすればもっと具体性が増したと思う。2013/01/04
tk
1
「(教師は)言うことを聞かせたり自分に従わせる経験は豊富ですが、人の言うことを聞いたり他人に従うことは不得意なのです。」(p153). 「(二つの瓶にご飯を入れ、それぞれにバカとありがとうという紙を貼っておくとバカの方が早くカビが生えるという教師の説明を受け)バカの瓶には唾がかかったんじゃないの?」(p176).2016/02/20
bombo9196
1
いかに公務員である教師に自浄作用を持ったシステムを導入するか。その1つとして最後の章では教師にも通信簿を、という提案がされている。2014/02/16
壱萬参仟縁
1
評者は10年以上は学習支援業をしてきた。この経験からしても、処遇面でかなり恵まれている教諭職や公務員ということである。学習支援以外にも生活指導があったりするのが違うが、官民交流制度がないのも問題である。例えば、予備校講師がうまい教え方を教えに行くのではなく、学校から塾にきて民間の論理で働くということだ。すると、民間のコスト感覚がわかるのだ。官民格差をなくし、同じ子供を育てる同志意識がない限り、双方の足の引っ張り合いになってしまう。2012/05/22
-

- 電子書籍
- 無職だけど異世界で世界滅亡の危機に立ち…
-
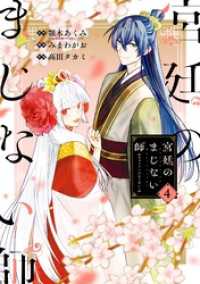
- 電子書籍
- 宮廷のまじない師 4巻 ガンガンコミッ…
-
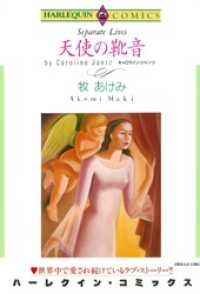
- 電子書籍
- 天使の靴音【分冊】 10巻 ハーレクイ…
-
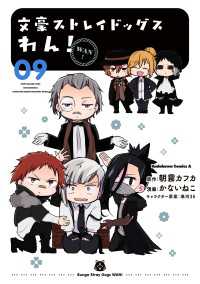
- 電子書籍
- 文豪ストレイドッグス わん!(9) 角…
-
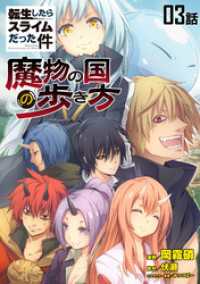
- 電子書籍
- 転生したらスライムだった件~魔物の国の…




