内容説明
僕は多くのことを考える。万一生きていたら、今夜を待って、とくと考えてみよう。ただ、生きているかどうか……。第二次大戦中、敗走するフランス軍に、一飛行士として従軍した作家サン=テグジュペリ。明日、ドイツ軍が侵入するであろう、祖国の一寒村にたたずんで、死を目前にした極限状況にあって綴られた、生の根源と人間の勇気に果敢に迫り、深く追究する思考。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Gotoran
44
1940年第二次大戦下、独軍に仏が占領される寸前の時期に、アラスでの独戦車部隊の偵察飛行体験をしたと云う著者。その壮絶な体験がベースとなった本著。アラス上空1万mで計器類が凍結する操縦室、他搭乗員との会話、敵戦闘機との遭遇、対空砲火、実にリアルな描写、鬼気迫る臨場感が伝わってきた。頁を捲っていくと後半では、(著者の思いとして)生死の狭間での幾多の深い省察が語られる。人間とって、国家とは?戦争とは?責任とは?義務とは?実に示唆深い。そこには、著者のストイックなまでの揺ぎ無い強い信念があった。2015/02/20
イプシロン
22
2013年に読書メーターに登録し、様々な本を読み思索してきたすえたどり着いた私の思想哲学に、ぴったり重なる思想に大変感激した。しかし、本著がもつ宗教性・哲学性の高さを鑑みると、ほとんどの人は読解できないレベルであろう。端的に言えば、一人は皆のため、皆は一人のためにがテーマである。これをキリスト教やスピノザの汎神論、カント哲学と絡めて話すことはできるが、本著でテグジュペリが述べている通り、言葉は誤解を生むだけだといえるだろう。絆を持ったうえで沈黙しつつの行為にしか情愛は宿らないというのが本著の趣旨だからだ。2025/05/14
高橋 橘苑
21
偵察飛行隊の操縦士として、生還は絶望的と考えられたアラス上空での戦闘体験を基にして書かれた作品。彼は祖国フランスの敗北を認め、単に軍事的な問題でなく、その拠って立つ所、キリスト教文明の高貴なる犠牲の精神が、集団の権利に対して敗北したのではと憂いを抱く。キリスト教云々を越えて、彼の高邁な精神が我々の胸を打つとすれば、それはなんだろうか。個人的な感想を言えば、人は土地や血縁や身の廻りの人間関係や、それが持つ文化を離れては生きられず、その中で自分の何かを犠牲にする事で、自分自身を証明したいと願うからだろうか。2015/04/02
たか
11
第二次大戦中、敗戦に向かうフランスでの体験を基にした本。淡々と語られるフランスの状況は絶望的にしか思えない。そしてアラスの飛行の描写が迫真。その壮絶な体験を経た後に語られる思想は、自らが行動者であった著者だからこそ実体をもち非常に力強い。「君は、君の行為そのものの中に住む。君の行為、それが君なのだ。」この言葉がとても好き。そしてそれが後半の「真人間思想」につながっていく。石が伽藍をつくるのではなく、伽藍が石を意味付ける。「個人は道でしかない」そこに立ち現れる信念、我が身を擲つ行動が人をつくる。2016/09/09
Porco
5
第二次戦下での仏軍偵察飛行部隊として戦争に参加した作者の実体験からきているのもあり、正直な話これは小説ではないと思う。軍が機能不全で敗色濃厚な状況で行われる馬鹿馬鹿しい危険な偵察飛行や、不毛な軍事作戦や兵士がただ行うだけの戦争遂行。本作はその有様を大空を飛びながら体感したサンテックス自身の無意識下にあった幻想、哲学、観念を文章化し小説という型に嵌めた自叙伝だ。2022/07/02
-
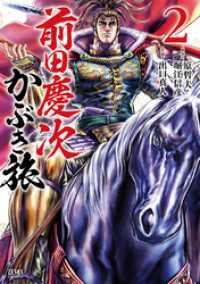
- 電子書籍
- 前田慶次 かぶき旅 2巻 ゼノンコミッ…
-
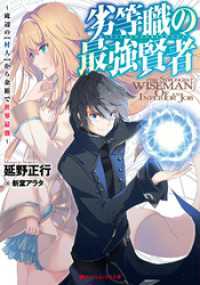
- 電子書籍
- 劣等職の最強賢者 ~底辺の【村人】から…
-
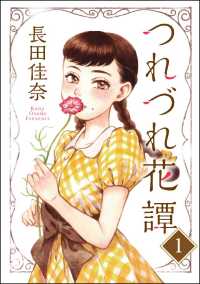
- 電子書籍
- つれづれ花譚(分冊版) 【第1話】
-
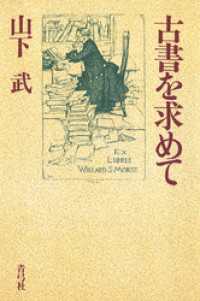
- 電子書籍
- 古書を求めて
-
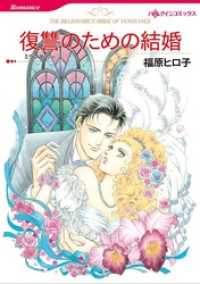
- 電子書籍
- 復讐のための結婚本編




