内容説明
近代日本の歴史哲学の草分け・三木清は、ヨーロッパ・ニヒリズムの思想的意味に目覚め、次第に激化しつつあった日本ファシズムに抗し、無法な拘禁の下に獄死した――。本書は、その著者の生き方、思索の足跡を偲ばせると共に、ある時は青春を、ある時は読書遍歴を、またある時は哲学の手引きを、真摯な筆致で読者に親しく語りかける。若い人々への読書案内として、必読の名著。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ケロコ
30
お風呂のなかで少しずつ読み進め読了。満腹だ。大正後期から昭和初期までに書き貯められたものが昭和19年に刊行されているようだ。それなのに全く色褪せていない。お風呂で体を温めながら少しずつ読み砕いたので、じっくり体に染み渡ったという感覚。この読書論は無駄がない。何度も読んで体の一部にしたいと思わせた1冊。2016/12/20
nobody
9
最後の「消息一通」で『哲学入門』の異次元疎外文体に戻る。『人生論ノート』でも同じやり口だった。書簡というより柔らかな形式に見せかけてのひっかけで、必須たる宛先の情報はなく、ハナから内実を伝える意図はないのである。でなければ新潮文庫編集部は、原語表記のドイツ語もハルトマンにおける認識論の問題点も日本の一般読者が素養としてもっていると看做していることになる。この狙いは内実ではなく三木の留学時の「勉学ぶりを伝える」(解説:山田宗睦)ことにあるのは明白だが、新潮文庫編集部は「著者がお前らみたいなパンピーと同じ所に2023/03/30
anchic
9
職場の上司に貸してもらって読みました。読書の方法についてはどれも正論すぎて反論の仕様がない程でした。自分にとっての生涯の一冊に巡り会うためにもしばらく濫読を実践していこうと思います。2013/04/25
無能なガラス屋
8
「如何に読書すべきか」という20ページに満たない章だけでも価値がある。実際、私はそこしか読んでいないが大満足だ。何の本だったかは忘れたが、読書術は人生の中で習得しなければならない必須技術の一つである、というような言葉がずっと私の中に残っていて、この本もその技術の改善・向上に貢献してくれた。「読む」というのは単純なことではなく、終わりのない階段のようなものだと最近気づき始めたのだが、階段を登ろうともせず、そんな階段があるとも思っていない人がいる。そういう輩に限って古典作品を一刀両断するような感想を書くのだ。2020/07/01
よこ見
7
著者の青年期や読書歴の回想中心のエッセイ集。20世紀前半の哲学者や哲学書等の固有名詞(しかも自分には聞き馴染みがない)がこれでもかと出てくる「読書遍歴」の章は中々ページが進みませんでしたが、その後はわかりやすい読書指南等が続いてスムーズに読み進められました。全体的には、概説書は一冊読めばいい、その後は原典、それも原語で読むのがいい、という昭和初期の教養主義的な厳しさを感じる内容でしたが、その分求道者のような矜持を感じさせるというか、読んでいて襟を正したくなる気持ちになりました。2025/09/29
-
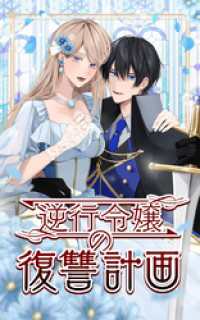
- 電子書籍
- 逆行令嬢の復讐計画 第35話【タテヨミ…







