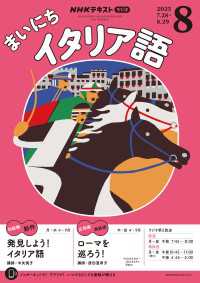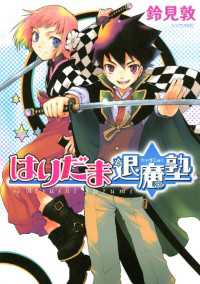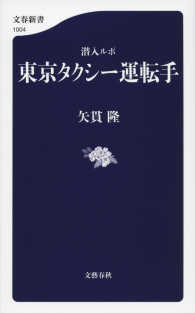- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
現代思想の問いは、言葉の問題に収斂する。世界を分節し、文化を形成する「言葉」は無意識の深みで、どのように流動しているのか? 光の輝き(ロゴス)と闇の豊饒(パトス)が混交する無限の領域を探照する知的冒険の書。(講談社現代新書)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
(haro-n)
71
ソシュールの言語論を知りたくて手に取ったが、それについては概説があったものの、メインはソシュールのアナグラム研究とその研究の限界、及びそこからの後の研究者らの言語の捉え直しについてだった。アナグラム研究とその導入で紹介されていた百人一首の話は、真偽の程は分からないがとても面白かった。死や性の問題等と同様、生きるエネルギーに直結するものとして言語活動(ランガージュ)を捉え直そうとする展開は納得できる部分も多く、興味深く読んだ。言分けや身分け等詳細は理解不足なので、再読や他の書物を当たる等して理解を深めたい。2018/11/07
ころこ
40
ソシュールの言語学は、構造主義に影響を与えただけでなく、アナグラムを通じてもっと大きなものに触れている。著者はそれを無意識と表現しています。自存的に意味があるのではなく、顕在・潜在的な場に織りなされるテクストの中においてのみ生ずる。深層表層モデルのやや古い感じのあるテクストで、無意識の神秘化が図られている嫌いがあります。現代思想の一部のテクストは見方を変えれば暗号解読でので、それらの読み替えのヒントになりそうです。本書は現代思想用語が使われていても、かなり読み易いので、勢いに任せて読んでしまえます。2019/05/14
hitotoseno
18
我が国最高の言語学者にしてポストモダニストである丸山圭三郎が言語に潜む無意識を軽やかに論じた小著。ソシュールのアナグラム論がなぜ行き詰まったかを「主体の意識にこだわりすぎたから」と診断し、ラカンやクリステヴァなどを引用しつつ言語がいかに無意識的に出来上がっているか、無意識がいかに言語的に出来上がっているかを横断的に論じる。ポストモダニズム的な思考が定着し、いかにそこから抜け出すか・突き詰めるかが姦しく議論される時代の中にあってこうしたスマートな佳作を読むことは一服の清涼剤を飲むようなものである。2017/01/15
Ryo
16
「言葉とは抑圧である」という言葉に至極納得。人が表現しているものや、常時感覚として得ているものは概ね、「ロゴス(言語域)>パトス(芸術域)>無意識」の3階層に大別される。そして言語域に存在するものは、言語を使用する文化と不可分であり、必ず文化という制度に拘束される事になる。これから多少なりとも自由になるには表現方法を増やして、言葉だけでニュアンスを伝えられる様にするしかない。そして、幸いな事に言語にはまだ意味性の揺らぎがあり、それをうまく使って表現域を拡げることで、パトスを表現できる可能性が残っている。2019/05/27
マル
12
『言葉』とは一体何なのか?ギリシャ時代から現代まで、人々が『言葉』をどのように考えていたのか。構造主義の祖のとされるソシュールさんの考えや精神分析家のジャック・ラカンさんの考えなども述べられていて、たいへん内容のある一冊なのですが、いまの自分のレベルでは本書の内容の半分も咀嚼できませんでした。「無意識が言葉の条件であるのではなく、言葉こそが無意識の条件である。言葉が無意識を作り出すのだ」というラカンさんの言葉。ふむふむ、なるほど(と頷いてみるもよく分かりません。すいません)。よく「日本には言霊信仰がある」2016/08/05