内容説明
日本仏教の歴史とは、「国家宗教」を民衆化するべく闘った思想家たちの歴史である。聖徳太子から空海、親鸞、道元、そして良寛まで、12人と思想から平易な言葉で解き明かす、日本仏教史。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
to boy
30
六世紀半ばに伝来した仏教が「日本仏教」として変化していく様をわかりやすく書かれていました。独創的な思想家7人、社会思想史として興味ある5人について思想、特徴などを初心者にもわかるように書かれていて読みやすかった。現代の仏教がなぜ葬式仏教になってしまったのか、人生の意味を教えてくれることがなくなってしまったのかへの批判は著者らしく痛烈です。今まで興味がなかった一遍上人に興味を持ちました。2018/01/06
かんやん
25
六世紀半ば百済経由で伝わった仏教は国家宗教として採用される(蘇我氏)。奈良仏教(聖徳太子)→平安仏教(比叡山の最澄と高野山の空海)は支配層のためのものだった。空海の真言宗(密教)は既にして完成され、発展はなかったが、比叡山の天台宗からは、法然(浄土宗)、親鸞(浄土真宗)、道元(曹洞宗)、日蓮(日蓮宗)、一遍(時宗)などが排出された。鎌倉仏教になって初めて庶民にまで浸透し、また異端として弾圧される。浄土への渇望や他力は当時の過酷な生ゆえであろうが、自分にはあまりに生々し過ぎて、一休の風狂に惹かれてしまう。2024/04/13
みずたま
5
仏教史と言いつつ、最後の江戸から明治、現代にかけての「キリシタンではない証明からの強制的な仏教化、葬式仏教と商売。その反動としての国家神道、そして無宗教の社会」という部分(多くは書かれていない)が、とても強烈に印象的だった。 日本人と仏教との関わり。この一冊ですべてを理解することはできないが、これまでの仏教と国家という印象からは少し違う歴史を垣間見れた。2019/02/17
Yoshihiro Yamamoto
3
B 「日本において仏教は、最初の最初から民衆や庶民のための宗教ではなく、支配階級のための宗教であった(鎮護国家や貴族の念持仏等。王法に対する仏法の独立がない)」「特に江戸時代に入ってからの「檀家制度」が仏教を完全に退廃させた」という筆者の仏教観をひしひしと感じる1冊であった。面白かったのは、平安時代は取捨選択の時代として、大乗仏教(最澄)vs小乗仏教、密教(空海)vs顕教、他力仏教(法然)vs自力仏教という軸で、選択が行われたという指摘だ。こうした選択を通して、仏教が日本化されたという筆者の指摘は面白い。2017/01/31
Рома
2
空海と最澄、法然と親鸞、似てるようで異なるそれぞれの考えの違いや日本における仏教の在り方の変遷は分かりやすかったが最後の国家神道や教育勅語への批判を無理やりするのはクソだった。2018/03/08
-

- 電子書籍
- ドラコラン【タテヨミ】第15話 pic…
-
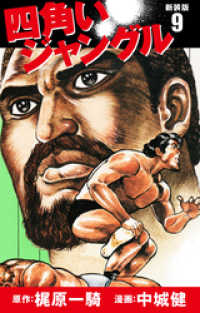
- 電子書籍
- 四角いジャングル(新装版) 9
-

- 電子書籍
- 紗綾 100%JUICY!
-
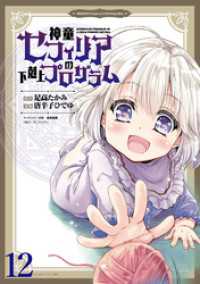
- 電子書籍
- 神童セフィリアの下剋上プログラム WE…
-
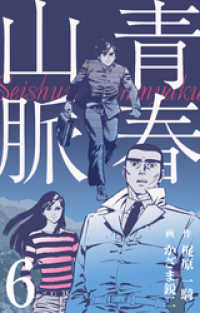
- 電子書籍
- 青春山脈6巻 マンガの金字塔




