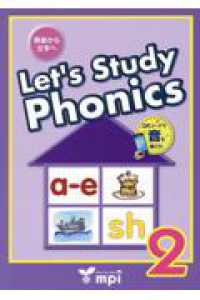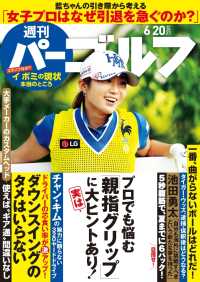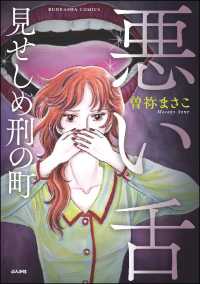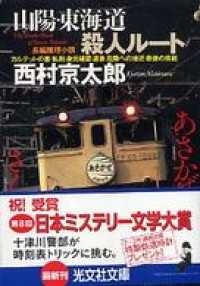- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
バブルが崩壊し日本経済は低迷の時代に入った。
崩壊後の四半世紀を検証することにより、その要因を導き出し今後の経済政策への指針を提示する画期的な書!
<執筆者>
竹中平蔵(慶應義塾大学グローバルセキュリティ研究所所長兼慶応義塾大学総合政策学部教授)
袖川芳之(電通ソーシャルプランニング局・プランニングディレクター及び慶應大学非常勤講師)
原田泰(日本銀行政策委員会審議委員、経済博士)
高橋洋一(金融庁顧問、大阪市顧問、経済学者)
藤田勉(シティグループ証券取締役副会長)
跡田直澄(経済学者、嘉悦大学教授及び副学長)
市川宏雄(明治大学専門職大学院長、ガバナンス研究科長、政治経済学研究科教授)
松原聡(経済学者、東洋大学教授)
曽根泰教(政治学者、慶應大学DP研究センター所長)
村井純(日本の計算機科学者、慶應大学環境情報学部長兼環境情報学部教授)
島田晴雄(経済学者、千葉商科大学教授)
真鍋雅史(嘉悦大学准教授)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
91
まだ出版されたばかりの本で慶応大学のグローバルセキュリティ研究所がバブル崩壊後の日本経済についての検証研究を行ってきたものをまとめたものです。一人の著者によるものではないのですが各分野ごとにその専門家が書かれているので、エッセンスということで読んでいけばいいのでしょう。財政、マクロ経済、社会資本、金融市場、社会保障、産業政策、雇用など若干表面的すぎるきらいがあるのですがさらっとおさらいをするにはいいのだと思いました。2016/06/25
お抹茶
1
安倍政権に肯定的な論者が多い。実質的な変動相場制は1980年代後半から。2000年のゼロ金利解除は失敗と評価。好景気・低インフレ・低金利がバブルの原因とされるが,最近は好景気・低金利でも,世界のインフレ率が構造的に低位安定しているので,景気刺激政策の効果は小さい。社会保障給付の抑制と景気の安定化・経済成長促進が財政赤字の抑制につながる。最低賃金引上げや派遣労働の規制強化,雇用調整給付金は,弱い労働者の雇用機会を減らし,企業淘汰も進まない。モノの所有と世帯収入が支える消費社会は1960年代が黄金期だった。2017/12/01