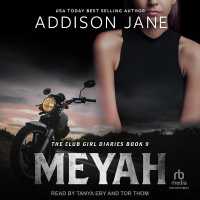内容説明
たとえ批判されても、これからの時代のために、建築をつくる。
新国立競技場を設計する建築家・隈研吾が、決意を語る。
建設予算の高騰、“景観破壊”批判などにより、ザハ・ハディド案が白紙撤回となり、
再コンペの結果、隈研吾が参加するプランが選ばれた。
“火中の栗”を拾った隈研吾のもとには、新プランへの様々な意見が寄せられている。
中には、日本の建築界を引っ張ってきた先輩建築家からの、思いもよらない批判もある。
だが、それでも、図面を引く。批判を受け止め、先に進むために。
コンクリートで作られた、スター建築家による“アート作品”ではなく、
人々が集い、愛される、「木のスタジアム」を作るために。
日本を襲った震災、そして、社会のギスギスした空気。「建築」そのものに対する強い風当たり。
あらゆるものを引き受ける意思はどこから来たのか。
なぜ今、「木の建築」なのか。余すことなく語る。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ビイーン
28
随分と世間を騒がせた新国立競技場だけど、結果的に隈研吾案に決まって良かったと思う。受け身で戦う姿勢に好感。木を使った競技場を見るのが楽しみだ。ザハ案は素晴らしいデザインだったのかもしれないが、周辺環境から浮いたエゴ丸出しのパワフルさは日本風と異なる大陸的感覚だと思うし、それを日本が世界に発信するのは違うだろう。2019/10/22
しーふぉ
25
隈研吾さんは木材や竹を上手に使うイメージ。関東大震災の教訓から一時は木材よりコンクリートへ移行されていたが、燃え難い加工の登場などから再評価されている。日本の文化をオリンピックという舞台で世界に発信するという意味では、ザハ・ハディットさんのデザインより隈研吾さんのデザインの方が良かった気がする。新国立競技場がどんな姿を見せてくれるのか楽しみです。2017/07/15
nbhd
16
個人的には、国立競技場が“ああなった理由”の説明よりも、“アートとしての建築の終焉”を結論付けたような現代日本建築家の系譜の方に興味をもった。第1世代に「総合としての丹下健三」、第2世代に丹下の「総合」を分割継承した「アートの磯崎新」「ポピュリズムの黒川紀章」「アーバニズムの槇文彦」。第3世代に磯崎のアートを継承するかたちで、独自の表現に至った安藤忠雄、伊東豊雄がいる。隈さんは第4世代。建築の本質は「調整」と言い、受け身や妥協を厭わない隈さんのスタイルは、アートすら否定しているように読めた。2017/05/31
アコ
16
建築家を志した原点が10歳のときに見た丹下健三氏の国立代々木競技場と代々木体育館だという隈氏。デザインビルド主流のいまの世の中に合う器が大きく柔らかな建築家だなと感じるし、実際ゼネコンチームとの風通しや『美しい妥協』を大事にする姿に好感。建材としての「木」に対する確信と信頼について長く述べており、コンクリートから木に戻る理由もわかりやすく伝わる。やはり後世に残る巨大建築物なのだから日本人設計は単純にうれしい。5-6章は大成建設と梓設計トップのインタビュー。ラスト7章めは茂木健一郎氏との対談。2017/03/18
tapioka
15
新国立競技場を巡り、採用されたザハ案が高額な建築費などの理由で再コンペとなり、大成建設と隅氏らがJVとして臨んだ案が採用された。その隅氏が今の新国立の設計思想など述べた本。ザハ案のような近未来的なデザインは立地から浮いた構造物で、すぐ飽きられてしまう。その場所の文化との調和を重んじる隅氏の方向性の方が、長らく受け入れる建物となりそうだと感じました。また、実際完成した新国立を間近で見ましたが、木が多く使用された外観は非常に良かった。一方座席が狭い等の批判はあるようですが、ぜひ自分で利用して体感したいですね。2020/03/07