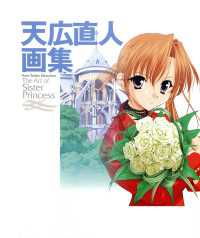内容説明
チベット、アフガン、トルコ、ペルシャ、イラク。第一次世界大戦後、西洋支配の桎梏から抜け出そうともがくアジア諸国の状勢を鋭く分析した「復興亜細亜の諸問題」。日米開戦前後にわたって綴った論考を収めた「新亜細亜小論」。東亜の論客はアジアに何を求めたのか。〈解説〉大塚健洋
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
叛逆のくりぃむ
10
北一輝と並ぶの国家主義者大川周明の主著。中東地域におけるナショナリズムの勃興を紹介、分析している。著者の学識の深さが伺えると共に、地域研究における今日的意義も失われていない。2016/04/26
大森黃馨
4
残念だが氏の主張には同意しかねる西洋植民地も独立さえすれば全ては万々歳的思想と激があるか経済や地政学そして国際政治とは何かの観点が欠けているように見えるまた日本の発展のレベルを買いかぶりすぎてはいないか一旦亜細亜植民地解放に取り組めばその先は泥沼化で我が国に破滅をもたらすのではないかやはり御家ならぬ御国は大事第一なのではなかろうかこの段階の我が国の西洋植民地亜細亜への関わり方は同書内でも記述されていたソ連的手法ないしは静的インテリジェンス的手法それもややこしくなりそうならすぐに撤退する覚悟で(続く)2022/10/05
てれまこし
2
インド哲学に一生を捧げようという学生が、偶然植民地インドの惨状を知る。志士的な義憤に駆られて政治経済も学び、アジア主義のイデオローグとなっていく。大東亜共栄圏は「仁」の機構化であるべきで、日本は指導者としての徳を行動で示すべきであると説く。一方で、「草莽崛起」型革命家とは違い、軍人、武断型政治家の役割を重視する。ここに政教一致の問題が未解決で残される。そして、同じ原理が大東亜共栄圏に適用されたとき、日本の指導的立場を他国は受け入れるよう要請される。ここに反植民地ナショナリズムとアジア主義の矛盾も残される。2019/06/21
かみかみ
2
英仏露といった国の植民地支配下におけるアジア諸国の趨勢や独立運動といった問題を分析した一書。世界大戦において宗主国の戦場の最前線に立たされる植民地の原住民の現状などが生々しい。大東亜戦争(太平洋戦争)の時下、イギリスの植民地支配を批判しつつも『管子』の記述を引用して同国の"give and take"の思想を全否定するような風潮に諌めていたのが印象深い。著者は東京裁判でA級戦犯として法廷に立ったという印象が強いので。2017/03/25
ゆーじ
1
これほど迄に近代亜細亜の歴史や国際関係を詳細に描いた本に巡りあう事はなかった。実に勉強になります。当時の亜細亜は欧米帝国の植民地争いのまっただ中にあり、ロシアを破った新勢力日本を植民地争いから除く事が列強国の共通の目標でもあったのです。実に当時の欧米帝国が亜細亜を蹂躙していたかをこの本は描いてます。今の紛争の原因も元を質せばこの頃の欧米帝国主義が落としていった火種にあったのです。 2023/10/31