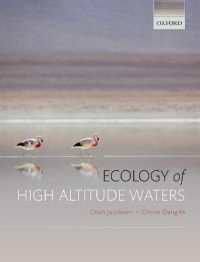内容説明
本書は不遜な歴史書だ!
ギリシャの「科学」はポエムにすぎない。
物理こそ科学のさきがけであり、科学の中の科学である。
化学、生物学は物理学に数百年遅れていた。
数学は科学とは違う――。
1979年のノーベル物理学賞を受賞した著者が、
テキサス大学の教養課程の学部生にむけて行っていた講義のノートをもとに
綴られた本書は、欧米で科学者、歴史学者、哲学者をも巻きこんだ大論争の書となった。
「美しくあれかし」というイデアから論理を打ち立てたギリシャの時代の哲学が
いかに科学ではないか。アリストテレスやプラトンは、今日の基準からすればいかに
誤っていたか。容赦なく現代の科学者の目で過去を裁くことで、
「観察」「実験」「実証」をもとにした「科学」が成立するまでの歴史が姿を現す。
解説・大栗博司 (理論物理学者)
1 ~ 1件/全1件
- 評価
Piichanの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
えも
25
あの物理学者ワインバーグの書いた科学史だから、やっぱり何だか偏ってます(笑)。まず「現在の基準で過去を裁く」という歴史学の禁じ手を使って、アリストテレスからデカルトからばっさばっさと斬りまくってる。ただし、その基準は理論や主張が間違っているからではなく、自らの理論を観測・実験で検証して発展させていくという、まさに「科学の方法」に則っていないという一点で批判してる。だから表題も、個々の科学法則の発見の歴史ではなく、あくまでも「科学(の方法)の発見」という意味なんですね◆やっぱ偏ってて面白いわ。2016/09/04
MAEDA Toshiyuki まちかど読書会
23
ルネッサンス後、数学で科学を記述するようになり、万人が科学を検証・発展できるようになった事が科学革命に繋がったと理解しました(^^♪2019/08/15
R
23
古代哲学から始まり、現代に続く科学にまつわる歴史を紐解いた本でした。凄い面白かったけど、大変難しかった。現在の科学知識から見て、当時の判断を裁定するといった内容だけども、その非凡さと失敗を丁寧に論述しているところが面白い一冊でした。科学の歴史において、哲学や神学という分野と隣接していたことが発展や、妨げとなっていたという話は興味深いし、偉人たちの凄みと、それでも失敗や、間違いがあったという事実指摘は物凄くためになりました。物理学、天文学に造詣が深いとより楽しめただろうなぁ。2016/08/30
わたなべよしお
22
良い本でした。ここで書かれている科学理論の詳細は、よく分かっていない。しかし、歴史を記述する軸、つまり現代科学の基準でみるという視点が明確なので、論旨は理解できた。望遠鏡で観測しただけじゃん、なんて思っていたガリレオがなぜ科学上の偉人なのか初めて分かった。勿論、ニュートンも。2016/07/24
Shin
18
現代の科学の知識に基いて過去の科学者達の在り方を批評する、というタブーを敢えて犯すことで、「科学とは何か(あるいは何が科学ではないか)」を炙り出そうとするスリリングな試み。結論が正しいか否かではなく、与えられた状況で最善の推論と検証を試みたかどうかで評価を下す姿勢は、論争を巻き起こしたという割には意外とフェア。「世界はこうあれかし」という哲学者の視座を科学から分離することで、科学と哲学(そして宗教)の境界線を画定することは、互いの世界観が人の世の役に立つために避けられなかった苦闘の歴史だったと分かる。2016/05/29