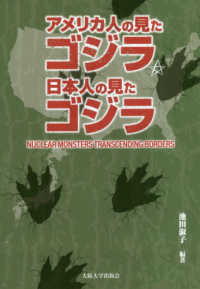- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
男子普通選挙とともに訪れた本格的政党政治の時代は、わずか8年で終焉を迎えた。待望久しかった政党政治が瞬く間に信頼を失い、逆にそれほど信望の厚くなかった軍部が急に支持されるようになったのはなぜか。宮中やメディアといった議会外の存在、大衆社会下におけるシンボルとしての天皇、二大政党による行き過ぎた地方支配など、従来の政治史研究では見過ごされてきた歴史社会学的要因を追究する。現代日本の劇場型政治と二大政党制混迷の原型を、昭和戦前期に探る試み。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
佐島楓
55
この題名の内容を扱った本は珍しいなと思い、キープしておいて、ようやく読めた。ほぼ知らないことばかりで、とても勉強になった。マスコミの力が政治に影響を与える構造は、この時代(1926~)からあったのね。2016/09/23
パトラッシュ
20
この著者は常に歴史の常識をひっくり返す。本書でも戦前の政党政治が8年余で滅びた原因、即ち未熟な政党による政治腐敗の凄まじさと政争に明け暮れる愚かさを描き出す。戦前の国政は永田町と霞が関だけでなく宮中に軍や貴族院など強い勢力が割拠し明確な中心を造らなかった帝国憲法の欠陥が露呈していたが、政党政治は警察やヤクザから市民までも系列化して自分たちの当選を安定させようとした。こんな政治に8年も付き合わされたら国民が忍耐の限界を超えるのも無理はない。戦前の政党政治は滅びるべくして滅んだのだ。小さな新書だが大きな一冊。2019/12/02
coolflat
17
加藤高明内閣から始まる憲政の常道がいかにして崩壊したのか。現在にも通ずる。日本は満州事変以後、破滅の道を辿る。そこには軍部の台頭(=政党政治の崩壊)があった。なぜ軍部の台頭が起こったのか(を許したのか)。それは民衆が政党政治を育てなかったという事が第一義的にある。内輪の政争に明け暮れる既成政党に嫌気をさしていた。メディアも政党政治を批判するばかりで、それを積極的に育成しようとはしなかった。そうした政党政治に対する忌避感が、第三極(軍部を筆頭とする軍部+官僚+警察=新体制)を誕生させる土壌になったのである。2017/04/05
masabi
11
【概要】昭和戦前期の二大政党制の成立と挫折を政争と議会外勢力の動向を中心に解説する。【感想】1924年から1932年までと政党政治は短命で終わる。普通選挙の実現により選挙資金の増大と大衆デモクラシー・メディアによる世論を招き、前者は多発する疑獄事件を、後者は劇場型政治を生み出した。結果、政党政治に対する信頼を失墜させ、腐敗した政党に代わり軍部が台頭する土台を提供することになった。戦前の教訓として、政党政治家、メディア、有権者いずれにも二大政党制を育てる意識に欠けていた。2023/01/20
G❗️襄
9
昭和の始め、藩閥政治を拒み、デモクラシーの流れから選挙による代表の政治、政党政治の時代が訪れた。 1924年(大正13)加藤高明内閣成立。民主主義の道を歩み始めるが、1932年(昭和7)515事件犬養毅首相暗殺、政党政治は僅か8年間で潰えた。軍部が政界に浮かびあがってくる時期、戦前日本の変節点となった時期である。何故、大陸情勢に目論む人間に引き摺られていると気付けなかったか悔やまれる。この間の六代内閣の詳説に触れる事は大変意義深い。今日にも通じる、民主主義政党政治の難しさが、既にこの時代から存在していた。2025/11/18
-
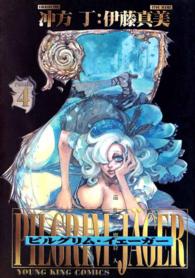
- 電子書籍
- ピルグリム・イェーガー(4)