内容説明
戦争に対しては、ビタ一文支払いたくないのが本心だった……戦後四半世紀を経て、自らの息子の徴兵忌避の顛末を振り返り、複雑な親心もまじえて語る「徴兵忌避の仕返し恐る」ほか、戦時中にも反骨精神を貫き通した詩人の天邪鬼ぶりが溢れるエッセイ集。
〈解説〉池内 恵
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kinkin
67
帯には「天邪鬼詩人の反骨言行録」と書かれていた。反骨とななにか、ただ大きな力を持った世論に対して反発することか、そうではなくそれを大声で体をもって示すことが反骨だということを知る。このほんに書かれているエッセイはどれも昭和30年以降のものだ、しかし著者は太平洋戦争中にも防空演習や、自分の息子を戦争に行かせないために様々なことを試したという。大きな世論に迎合することは簡単で居心地よくともそれが自分の身の上にのしかかる頃に息苦しくてそのうちどうにも耐えられなくなるのだろう。見せかけの自由への疑問の大事を知る。2016/12/25
tsu55
17
日本人的な(長い物には巻かれろ的な)奴隷根性を批判する一方で、権力に対峙するはずの所謂進歩的文化人の甘さに対しても厳しく批判している。生半可な覚悟で反戦、平和と叫んでいるだけではどうにもならないのだ。反骨を貫くには、図太いしたたかさが必要なのだということを知らされた。2016/08/31
モリータ
11
池内恵氏が解説ということで。文学部は「市民社会」の成員を養成するところ、とのこと。2016/05/11
グッダー
6
金子光晴さんのエッセイの中で一貫しているのは、大衆主義への疑いと、日本人の奴隷根性とも呼べるような封建的な思想への危機感である。 自らの戦争体験に裏付けられた日本人の国民性への危機感から、金子光晴は「なまけもの」を標榜することを選んだ。「なまけもの」は、大衆の中へ埋没せずに一歩離れたところから世間を見ることができる。大衆は変革が起きれば、自身の思想や人格までも変わってしまうものである。(つづく)2016/07/26
のうみそしる
2
戦争はどんなにひどいものだったか、当時の「抵抗」がどれほど命懸けだったか、いかに日本人が成り行き任せか、などが綴られている。言葉に重みアリ。「人に頼って自分の意見を変えるってことは弱いことだ。(中略)僕は、偶然だれもいなかったってことにすぎないけど。」2018/01/22
-
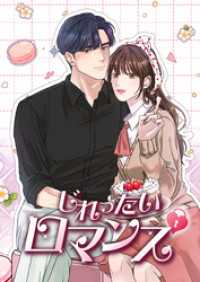
- 電子書籍
- じれったいロマンス【タテヨミ】55話 …
-

- 電子書籍
- 毒殺される悪役令嬢ですが、いつの間にか…
-
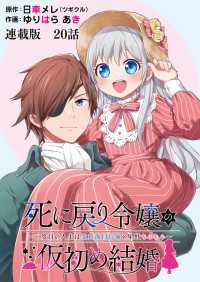
- 電子書籍
- 死に戻り令嬢の仮初め結婚~二度目の人生…
-

- 電子書籍
- 主人恋日記【マイクロ】(6) フラワー…
-

- 電子書籍
- 「めんどくさい」がなくなる本




