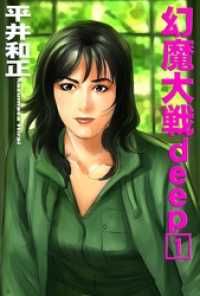- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
SNS時代に必要な文章術とは? 短くて、しかも絵文字が出てくる文章を書くのは容易だ。それよりも、誰もが短い文章を書く時代になったからこそ、長くても、わかりやすい文章にすればいい。語彙を増やし、句読点を減らし、それでいて読みやすい文章を書くことが、これからのビジネスパーソンにとっては絶対に必要になってくる。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
江口 浩平@教育委員会
32
【文章術】読書メーターで気の利いた書評を書きたいと思い、手に取った。読みやすいのだが、その分残念ながら強く訴えてくるものも少なかったように思う。本書でとりあげられている、人名や単語を中途で改行する「なきわかれ」というのを実際にしてしまったことがある。自分が教師になりたての頃に参加したセミナーで、講師の先生に読んでいただくために書いた感想文。「こういうのはしないほうがいいんだよ」と言われ、当時はすんなりとは受け入れられなかった。今となっては失礼だったなと思う。そのことを思い出させてもらった一冊だった。2019/06/26
はるき
23
ちょっと分かりにくいかな。もっとこう、イロハのイの字の書き方を詳しく教えて欲しがった。2017/01/14
サルビア
14
著者は、周りの人たちが夢を持っていると知り、自分も夢を持つことにした。それが、1冊の本を出すことだった。そんな著者には、文章術の師が二人いた。その二人の師に教えてもらい、念願の本を出すことが出来たと言う。著者は、まったくの素人だった自分が文章術を伝授してくれる。 sns時代には、短くて書いた人の意図がすぐわかる文章が求められていると説いている。今の時代、読み手を意識する事の大切さをあげている。また、著者がインタビューを申し込んだ時の話は、相手の心を動かすとはこういう事か、と心に残った。2017/07/23
またの名
7
スマホで見れる文章を毎日大量に読み込むのが仕事の電通社員が働いてる時代には明らかに、個々の言語使用から言語総体までがネットに寄せて変化。プロが手腕を駆使し書いた文章は強過ぎて浮いてしまうSNSの媒体で書くなら、SNS環境に合わせてプレーンな淡々とした文章を使いこなすことがプロでも必要と本書は訴える。王道の文章訓練法を一通り挙げてるのは当然として、ひらがなの多用が別に読みやすさを必ず実現してくれるわけではないので漢字や古めかしい熟語や専門的なタームを入れる時は入れるといった細かめのテクニックも、幾つか言及。2023/02/01
kou
6
タイトルと帯に惹かれて買ってみたけど、なんとなく求めていたものとは違った印象だった。句読点を減らすのと漢字とひらがなを使い分けて文章をデザインするってことだけは残った。どうやったら自分の文章が人に届くのかを意識する。確かにそうなんだけど、読書メーターにしろtwitterにしろ、自分が文章を書く場っていうのは、人に伝えたいとか認められたい以上に、単なる自己満足の場だからな… 詩を読むっていうのが新たな可能性を秘めてるのはいい発見。2016/11/18