内容説明
誰もが願う「より健康に、より長く生きたい」という希望。iPS細胞による再生医療をはじめ、出生前診断、遺伝子治療やロボット技術――最新のバイオテクノロジーに根差す現代医療は、その願いを着実に実現しつつあり、「病気や老化を克服する」可能性さえも見えてきた。
ところが、従来不可能であったことが「できてしまう」ようになることで、私たちはこれまで想像もしなかった課題に直面しつつある。それはたとえば、「技術的に可能なら、人工的に人のいのちをつくり出してもよいのか?」「身体の特徴や能力、知性などを親が好きに選んで、子どもをデザインしてもよいのか?」など、今日の倫理観では対処できないようなジレンマだ。そしてそれらは、テクノロジーが発展するほどにますます複雑になっていく。人がただ望むままに進んでいくならば、私たちはやがて「いのちをつくり変える」領域に踏み込んでしまうのではないか。
本書では、バイオテクノロジーがもたらすこのような治療を超えた医療=エンハンスメントの課題と、生命科学と深く結びついた現代、そして未来の社会を生きるための新しい“いのちの倫理”を、読者とともに「哲学的」に考えていく。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
5 よういち
97
医療の基本は、治療であるが、最先端の医療技術やバイオテクロノジーは、「普通に機能する身体を、それ以上のものに変えていく」ことが可能だ。これをエンハンスメントという。エンハンスメントは、『いのちを選ぶ社会』につながりかねない。ハーバード白熱教室などで有名なマイケル・サンデスはいう『エンハンスメントによって人間が自由であるための前提となる人間の在り方が掘り崩されてしまう。命は授かりものという感覚の中に、これまで人が大切にしてきたものがある』と。 それは、思い通りにならないことも受けいれるという人の知恵なのだ。2020/01/22
ニッポニア
42
いのちは作れる、ようになってしまった時代の倫理。以下メモ。命を作っても良いかどうか社会が決める。永遠の命を作る。手塚治虫の予言。幸福に満ちた命をひたすら求めるような未来は、限りある命と言う真実を遠ざけてしまうのではないか。再生医療で体を取り替える。治療を超えた医療。誰が決め、誰が選ぶのか、命を選ぶ社会。命を作り替える、人間の品種改良。日本は堕胎や間引きを受け入れてきた、殺すということではなく、生まれる前に帰ってもらう。個人の意識に還元される。生も死も他者との間で起こるつながりの中の命。雪が降る。2025/02/03
kakoboo
19
治療とエンハンスの違い、人間がより良い生活のための生命科学、でもやりすぎると。。。多くのことはどこで線引きをするか、その論争は文化や思想といった背景をとおして見るとなんとなく見えてきます。いまの段階では行ったり来たりな感じがして消化不良ですが、何と無く良書っぽいのでいくつかのテーマ(楢山節考、すばらしき新世界、サンデル教授の哲学的倫理思考)を深めていった上で改めて読み返したい本です。2018/04/29
樋口佳之
14
SF的な話は議論の上でだけで済むけれど、出生前診断は既に実用化されており、身近にその体験者はいる時代に入っている。生命科学の可能性が大きく報道される一方で、本書に書かれている、簡単な正解など無いにせよ、考える事を放棄してはいけない事柄が蔑ろにされている気がします。/「(堕胎や間引きについて日本の)民俗学的な研究によれば、ここには「殺す」ということではなく、「生まれる前に帰ってもらう」という観念があった、と理解されています。」/日本にある、中絶と脳死についての態度の対称性/なんだか法話を聞いた様な気分。2017/09/18
makimakimasa
8
段階を踏んで話が広がってくのが分かり易く、大学の良質な講義に実際に参加している気になる。手塚治虫の未完の遺作『ネオ・ファウスト』から、日本の脳死議論に一石を投じた柳田邦男『犠牲』まで、参考文献も豊富。治療を超えた医療「エンハンスメント」の矛盾や、命を「授かりもの」と考える意味の深さ。キリスト教は、受精の瞬間から神の似姿である神聖な人間と見なすが、他の被造物より特別たらしめているのは理性との見方から、中絶に厳しい一方で脳死は人間の死と認めやすい。そうした生命倫理学の基礎知識を含めて一通りのトピックを学べた。2022/12/02
-
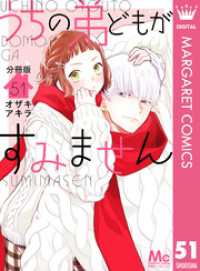
- 電子書籍
- うちの弟どもがすみません 分冊版 51…
-

- 電子書籍
- 中国から日本企業は撤退せよ







