内容説明
未曾有の福島第一原発事故から5年。政府は、原発避難者を消滅させようとしている。
国と福島県は2017年3月末までに、原発避難者の住宅支援を打ち切ると表明。約11万人とも言われる福島県内外の避難者たちに、事故前に住んでいた自宅に戻るのか、あるいは新天地で生きるのかを選ぶよう迫っている。これは避難という状態にとどまることを認めず、実質的に避難者という属性自体を「消す」ことを意味している。
2015年春夏、政府は「復興加速化」そして「自立」を前面に、原発避難の終了を迫る政策を打ち出した。最も線量の高い「帰還困難区域」(年間50ミリシーベルト超)を除いて、2017年3月末までに避難指示を解除し、その1年後までに月10万円の精神的損害賠償を打ち切る方針を決めた。
そして福島県も同じ2017年3月末までに、自主避難者や解除後の区域からの避難者への住宅提供を打ち切る方針を示した。さらに自主避難者の支援を目的とした「子ども・被災者生活支援法」についても、支援を「撤廃・縮小」する方向性を打ち出した。原発事故は自然災害とは異なり、原因者(加害者)が存在する人的災害である。避難生活を支える住宅と収入を提供する責任があることに異論はあるまい。原発避難について考えるとき、もちろん当事者一人一人がどう考えているかは大事だ。だが政治、そして社会が一人一人の意思、選択を大事に取り扱っているか、避難者の意向をくみ取り、制度として反映しているかを見定めていく必要がある。それが伴わないのは「棄民政策」に他ならない。原発避難者の生活基盤である「住宅」について、政府がどう決めてきたのか、そして避難者たちの思いがいかに踏みにじられてきたのか。政治家や役人たちによる被災者切り捨てのあざとい実態を、気鋭の記者が徹底追及する。
目次
【目次】●序章 避難者漂流●第1章 原発避難者とは誰か●第2章 避難者を苦しめる不合理な住宅政策●第3章 みなし仮設住宅―無責任の連鎖●第4章 官僚たちの深い闇●第5章 打ち切り―届かぬ声●終章 終わりになるのか
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
hatayan
八百
百太
まさ
チェアー
-

- 電子書籍
- 私、寂しいの… 村上沙織 爆ヤバDIG…
-
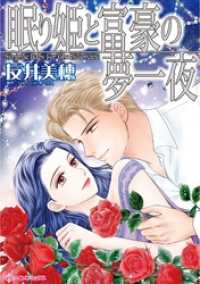
- 電子書籍
- 眠り姫と富豪の夢一夜 ハーレクインコミ…
-

- 電子書籍
- 狂蝕人種 (2) バンブーコミックス
-
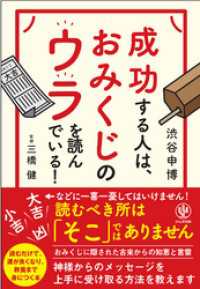
- 電子書籍
- 成功する人は、おみくじのウラを読んでい…





