内容説明
単語も文法も知らない赤ちゃんが、なぜ母語を使いこなせるようになるのか。ことばの意味とは何か、思考の道具としてどのように身につけていくのか。子どもを対象にした実験の結果をひもとき、発達心理学・認知科学の視点から考えていく。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
339
著書の今井むつみ氏は、認知科学・言語心理学・発達心理学の専門家。本書は生まれ落ちた赤ちゃんが、どんな風に言語を修得していくのかの仕組みをわかりやすく解説したもの。極めて刺激的で面白い。また、まだ言語を話さない(話せない)乳幼児を対象に、どんな実験を試みることでそれを知ることができるのかといったアプローチもひじょうに興味深いものがあった。人間が言語を修得するのは、既に母親の胎内にいる時から準備がはじまっているらしい。それなら、胎教もそれ相応に有効なのかも知れない。それにしても、これを読んでいると⇒2025/02/03
樋口佳之
54
その能力がいつどのように何故備わったのかとかという疑問が残りましたが、プリマーらしく読みやすいお話であったと思います。言葉の獲得過程と、科学の研究過程がパラレルであるとかなるほど。システムとして世界を把握しようとする能力、進化の過程の何処で備わったのかな。2023/03/29
さっちゃん
44
赤ちゃんの言葉の習得過程は思った以上にすごい。何も考えないで真似しているだけかと思ったら、ちゃんと日々フル回転で頑張っていたのだなぁ。これからお母さんになる人や乳幼児がいる親御さんは、読んでみると子育てがより興味深いものになるかも。2020/11/04
kei-zu
38
「言語とは、認識である」 赤・青・緑の色彩は明確な区分があるわけでなく、グラデーションの一定区間をそれぞれ定義したものである。「orange」は、日本語が想定するほど赤に寄っていない。したがって幼児は、認識能力が一定以上向上するまで、(「色彩」を認識しても)色を口にすることができない。なるほどね。 一方で、幼児の認識と言語の認識の向上能力は、めざましいものがある。 世界の認識の手法は、科学的なアプローチと大きく重なるとのこと。 知的好奇心がくすぐられますな。2020/10/15
あちゃくん
35
自分では何の気なく言葉を覚え使いこなしてきたつもりでしたが、その習得過程についてはほぼほぼ知らなかったなと気づかされる本でした。2022/12/23
-

- 電子書籍
- たむろ未知傑作サスペンス 4巻
-

- 電子書籍
- 日陰のアミル 追放されて無双する最強弓…
-

- 電子書籍
- WORLD SOCCER DIGEST…
-

- 電子書籍
- 彼女が公爵邸に行った理由【タテヨミ】第…
-
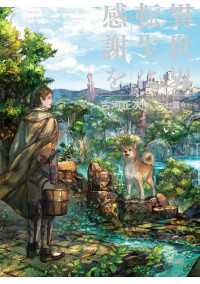
- 電子書籍
- 異世界転生に感謝を 7 ―




