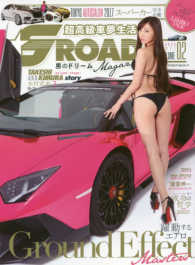- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
二四時間モバイル機器を手放せず、情報産業に囲い込まれた現代人の生活。人間が二足歩行へと進化した文字を持ちはじめた時から宿命づけられたこの現象は、二〇世紀に、二つのメディア革命を経て加速する。写真・電話・映画などの技術が人間の意識できない瞬間を記録し、広告・マーケティング技術が我々自身より先に消費・欲望を生み出し、デジタル機器が人間の生活全体を統治していく。人間は自分自身の意識をもう一度わが手に取り返すことはできるのか。そのために何ができるのか。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
佐島楓
34
あまり現在の自分に必要な情報がなかったのが残念。2016/04/10
kana
31
改めてメディア論おもしろい。こういう概念が好きだからこの仕事選んだのもあるなーと終始わくわく。メディアを用いることが人間の意識をどう変えたのかをソクラテスの問答にまで遡って探った後、記号論と結びつきどう整理されていくのか、20世紀のもたらしたメディア革命(アナログ/デジタル)が社会にどんな影響を与えたのか、我々はメディアとどう対峙すべきかなどがわかりやすくまとめられています。特に【写真は、あなたが見ることのできない瞬間を撮っている】に始まる「テクノロジーの文字」に関する言及は秀逸で何度も読み返したくなる。2021/05/15
tetsu
17
★5 これはすごい本に出会ったかも。 マスメディアが大量消費の需要を生み出した時代から、 個人個人が意識していない欲望をデジタル空間のアバターが先取りして教えてくれる時代へ。 AIが人間の生活を統治してゆく時代に入ったのでしょう。 メディア・テクノロジーの発展が生み出した現在社会を人間の生理学的特性など交えで解説する、ちょっと難しいけどなるほどと納得できる内容。 3章 現在資本主義と文化産業 4章 メディアのデジタル転回 5章 注意力の経済と精神のエコロジー 2018/03/16
しゅん
14
『新記号論』の良い復習になったように思う。ここでの感想・レビューもそうだが、だれもが統一されたフォントを使用しており、記号自体が同じになってしまっていることが問題だと最近思うようになった。本書は映画もレコードも活字同様の「機械が書く(人間は書けない)文字」として捉えており、そこからデジタル(数字記号への書き換え)移行を考えている。だれかが発明した便利な記号やシステムに頼る万能者、つまり「補助器具をつけた神(フロイト)」としての現代人間の限界を見定めるために、補助としての機能を十分果たしてくれる。2020/08/03
みのくま
14
とても興味深く読んだ。メディアは、思い出や遠くの光景の知覚、運動視、音声など「意識」を生産する。しかもその生産は、人間の知覚よりも下で人間の認知に働きかける「技術的無意識」を基盤にしている。つまり、現代人の「意識」の大部分はメディアによって作られているといっても過言ではないのだ。問題は人間がメディアを知覚できない事で、著者はその対策を呼びかける。(メディア・リテラシーの章はつまらなかった。)ちなみにこのような知覚できないメディアを「亡霊」と位置付け、現代人の「亡霊的生活」と評しているところが良かった。2017/07/23
-

- 和書
- 松下電器に明日はあるか