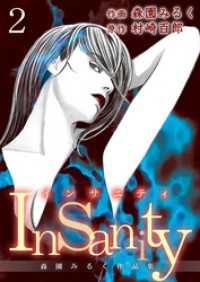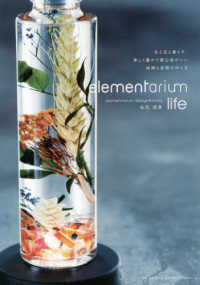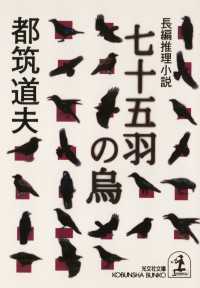- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
昭和初期の北樺太石油、満洲国建国時の油兆地調査、そして東南アジアの南方油田。
そこには確かに石油があったのに、日本はモノにできなかった。そして石油政策なきまま、戦争へ突入する。
43年間、商社でエネルギー関連業務に従事し、現在はエネルギーアナリストとして活躍、『石油の「埋蔵量」は誰が決めるのか?』(文春新書)を上梓した著者が、戦前、戦中の石油技術者の手記を読み込んで明らかにした戦後71年目の真実。そこには現代日本のエネルギー政策への教訓があった。
第一章 海軍こそが主役
第二章 北樺太石油と外交交渉
第三章 満洲に石油はあるか
第四章 動き出すのが遅かった陸軍
第五章 対米開戦、葬られたシナリオ
第六章 南方油田を奪取したものの
第七章 持たざる者は持たざるなりに
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
さきん
38
こういう本は本当に読む価値を感じる。自分も個人的に疑問に思っていた。最大の要因は陸軍の石油に対する理解の低さ。戦車、爆撃機の重要性が把握されるころには1930年代も後半に入っていた。日露戦争での成功体験も仇になったのか、石炭中心から中々切り替わることができなかった。油田を発見していたとしても、精製、保存、輸送する技術が未熟だったことも否めない。油田を発見したから太平洋戦争を戦い抜けたという単純な話じゃないということは痛感させられた。2018/07/28
金吾
28
場当たり的かつ論理性がない当時の日本の姿がよく表れています。日本は戦略的思考が苦手と言われてますが、それ以前の話かなとも思いました。まあ油田を確保したとしても輸送を考えていないのでどうしようもない話かなとも思いました。2024/01/08
coolflat
25
日本は戦争において、石油そのものが重要になることは認識していても、発掘~製造~輸送に至る統一された石油政策の重要性を認識していなかった。日本の石油政策は常に場当たり的で、敗戦の一因であった。それを象徴するものとして、当時の日本海軍は、大艦巨砲主義で商船護衛の思想を持たなかった。日本海軍の使命は敵艦を攻撃し勝利を得ることであった。1943年後半から米軍によるタンカーを含む日本商船の撃沈比率は高まっていた。海軍が商船護衛をしないため、南方で石油を製造しても日本に運ぶためのタンカーが到着しないという有様だった。2020/10/07
鯖
21
日本は三度エネルギー危機に襲われた。東日本震災、オイルショック、そして先の大戦。政府や軍は産油地を占領しても石油が湧いて出る訳ではなく、精製、加工、輸送と専門の技術者が必要だという認識に欠けていた。海軍以外は石炭から石油にエネルギーが変化したという認識に乏しく「水からガソリンを作る」という詐欺に近衛が引っかかりかける始末。…でも松ヤニで飛行機を飛ばそうは完璧詐欺だよなあ。タンカーが攻撃されると想定すらしていなかったとのことで、なんかもう前提からして全部だめじゃん…。2019/10/20
Porco
20
日本が東南アジアに攻め込んだのは、米国から石油が入ってこなくなったため、蘭印の石油を我が物にしようとしたからだ、とはよく聞く話なのですが、当時の日本の具体的な石油事情はほとんど知りませんでした。『海賊とよばれた男』にいくらか書いてあったのかも知れませんが。まず、石油についての理解が浅かったんですね。2017/05/24