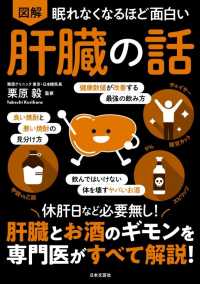内容説明
勇将・真田信繁(幸村)は、「真田丸の戦い」で圧倒的多勢に無勢にもかかわらず、なぜ徳川軍を打ち破ることができたのか。そこには「日本一の兵」と称されるに相応しい大胆な戦略と、脈々と受け継がれた城づくりの知恵が隠されていた。城郭考古学の第一人者が、最新調査と史料の新解釈から真田氏の実像に迫るとともに、「城」を手掛かりに群雄割拠する戦国時代を読み解いた力作。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
優希
109
真田丸の通説を大きく覆す説が興味深かったです。真田丸は単なる大坂城の出丸ではなく、1つの独立した城郭であったという説を取り上げ、その謎へと迫っていました。まだ発掘調査が終わっていないようですが、その概要をつかむことで、信繁がいかに力のある武将だったかがわかります。また、他の戦国大名たちの城の分析もなされており、「城」をキーワードに戦国時代を解明していく視点が面白いと思いました。2016/11/10
Kentaro
32
大阪夏の陣や冬の陣を通して、徳川家に相応の痛みを与えた真田信繁は、江戸時代に入ると、庶民の幕府に対する反発や、反体制的な不満を反映してか、徳川幕府の祖にして東照大権現という神にまで祭り上げられた徳川家康を苦しめ、庶民のヒーローとして愛されるようになった。 そして信繁の活躍には様々な尾ひれがついて、肥大化した英雄像が形作られるようになります。いつしか幸村という名前で呼ばれるようになったのは、ヒーロー物語としてフィクションの登場人物名が発端だ。 本書は真田丸の本来の大きさの新説も紹介している。2019/07/25
ようはん
24
真田丸は手薄な南方の平地に作られた砦というのが通説であるが、実際には真田丸付近は起伏が激しかった。よく言えば天然の要害であるが悪く言えば本城との連携が取りにくい場所に築かれ、ほぼ孤立した強固な要塞であったという。現地では真田側が掘ったという抜け穴が伝わっているが著者の考察では徳川方による塹壕の跡、つまり塹壕戦があった可能性があるというのも印象的。兄信之らが徳川方におり疑われやすい信繁の複雑な立場もあるが、それまでの真田の歴史を思えばある意味では得意とした状況であったろうか。2025/07/20
さつき
19
従来、真田丸は大坂城の弱点であった南方を守るために作られた「丸馬出し」だとされてきました。著者は『浅野文庫諸国古城之図』という図面集の絵図と、実際の地形などから真田丸は惣構との間に200メートルの谷で隔たれ孤立した小城だったとしています。あえて徳川方の目標となり、敵をひきつけるために築いたのだろうとのこと。圧倒的多数の敵を目前に控え、背水の陣の決意で真田丸に籠った信繁。読んでいて胸が熱くなりました。大河ドラマ真田丸を見るのがますます楽しみになります。2015/12/10
のぶさん
7
城跡考古学の視点から真田丸がどういうものであったかを解説。また、真田氏が築いた他の城についても言及している。そこから、真田信繁が当初から英雄として招かれたわけではなく、外様の立場でベストを尽くそうという姿が浮かび上がってくる。2021/10/06
-

- 電子書籍
- 婚約者の浮気現場を見ちゃったので始まり…
-
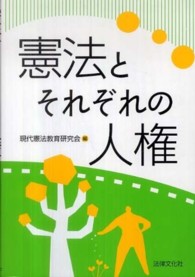
- 和書
- 憲法とそれぞれの人権