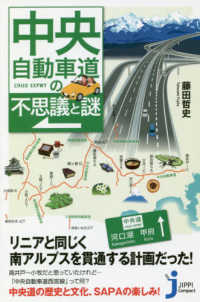内容説明
明治・大正期の作家たちの描いた「山怪」作品を斯界の雄・東雅夫の選で集成。
山の裏側を垣間見るかつてないアンソロジー。
われわれ日本人にとって、最も身近な「異界」である山々は、山神や山人、鬼や天狗、狐狸や木精といった魑魅魍魎のふるさとであると同時に、
日本の怪談文芸や幻想文学の豊饒なるふるさと、原風景でもある。
近代の文豪から現代の人気作家まで。
数多くの作家が、深山幽谷を舞台とする神秘と怪異の物語を手がけてきた。
本書は、山を愛し読書を愛する人々にとって必読の名作佳品を集大成した史上初のアンソロジー企画。
収録作品:
火野葦平「千軒岳にて」
田中貢太郎「山の怪」
岡本綺堂「くろん坊」
宮沢賢治「河原坊」
本堂平四郎「虚空に嘲るもの 秋葉長光」
菊池寛「百鬼夜行」
村山槐多「鉄の童子」
平山蘆江「鈴鹿峠の雨」
泉鏡花「薬草取」
太宰治「魚服記」
中勘助「夢の日記から」
柳田國男「山人外伝資料」
編者解説(東雅夫)
ほか。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
HANA
65
文豪たちが山を舞台として描き出した数々の奇談。古典的な怪談から夢の中を彷徨うようなものまで何でもあり。有名作品が多く三分の二は既読であったが、いいものはやはり何度読み返してもいいものだ。面白く読めたのは柳田國男「山人外伝資料」や美しい文体に酔う鏡花「薬草取」、幻視を描いた宮沢賢治「河原坊」といった所。他にも神話を思い起こさせるような火野葦平「千軒岳にて」やストーリーテラーの面目躍如な岡本綺堂「くろん坊」もまた巻を置くことあたわず。山が異界であるという事を、華麗な文と共に思い出させてくれる一冊であった。2016/02/07
たいぱぱ
59
明治〜昭和初期に活躍した文豪たちの山の怪異小説の短編集。読みにくいが文章が美しいかも。変態的に山登りをしてる友達のお膝元・静岡県の秋葉山が出てきたんで何やら嬉しく思ってたら、今度は鈴鹿峠が!知ってる所が舞台だとより興味深い。柳田国男の「山人外伝資料」が一番面白い!後に撤回したみたいですが、山人=真の日本の先住民という説は僕も賛成です。鬼は完全にそうだと思ってるのですが…。そこに南方(熊楠)くんと書いてある文章や木内昇さんの本で登場した鈴木牧之の「北国雪譚」が出典されてた事が我が事のように嬉しかったです。2025/08/13
そうたそ
36
★★☆☆☆ 山をテーマとした文豪たちの怪談作品を収めたアンソロジー。出版社が山と渓谷社というのもなるほど、という感じ。これをホラーアンソロジーと思って読むと、なかなかの肩透かしを喰らうのではないかと思う。「広義の怪談」というイメージで読むほうがいいかも。作家陣も知っている人と知らない人が半々。宮沢賢治、太宰治、岡本綺堂あたりの有名どころはやはり楽しく読めたものの、半分ほどはしっくりくるようなものではなく、結果としては自分の期待していた内容とは違ったというのが正直な所。着眼点が面白いアンソロジーではあるが。2016/02/21
深青
29
文豪達が描いた山にまつわる怪奇なお話を集めたアンソロジー。読んだことがない人が多かったので、面白く興味深く読みました。怪談というよりも山に対する畏敬の念を、山の不思議で怪奇な1面を描いた小説が多かったかなと。ちいとばかし読みにくいと思うものもあったり文字を追うので精一杯だったり……というものもありました。そういうのも含めて面白かったです。これを機会にここで出会った文豪の他の作品も読んでみようと思います。2016/03/07
YO)))
22
村山槐多の極めて絵画的な幻想譚「鉄の童子」、優しい鏡花の「薬草取」、柳田國男の山人論「山人外伝資料」など。 山を題材にしたものというだけで、形式・出来にかなりバラツキがあるが、それなりに楽しく読めた。 太宰の「魚服記」は澁澤龍彦編「変身のロマン」にも入っている。2019/10/03
-

- 電子書籍
- ユア・フォルマ【分冊版】 15 角川コ…
-

- 電子書籍
- 親バカ暴君の溺愛日記【タテヨミ】第12…
-
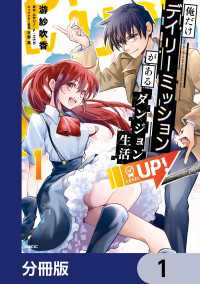
- 電子書籍
- 俺だけデイリーミッションがあるダンジョ…
-
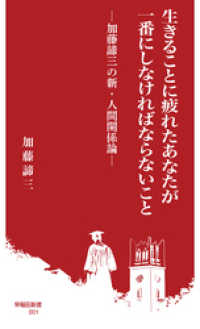
- 電子書籍
- 生きることに疲れたあなたが一番にしなけ…