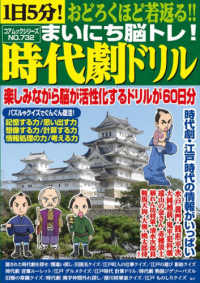内容説明
稀代の作家・ジャーナリスト・編集者カール・クラウス(1874-1936年)。ただ一人で評論誌『炬火』を編集・執筆し、激動する世界の中で権力や政治の堕落・腐敗に〈ことば〉だけで立ち向かったクラウスは、ベンヤミンやウィトゲンシュタインが敬愛した人物にほかならない。著者が深い思い入れと情熱を注いだ本書は、生い立ちから雑誌での活動、代表作の紹介まで、巨人の全貌を描いた日本語による唯一の書物である。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
masabi
19
【要旨】ウィーンの諷刺家カール・クラウスの解説。【感想】その著作は言葉遊びが満載で翻訳では自ずと限界にあたる。言葉の使い方ひとつ、句読点の打ち方ひとつを捉えてきらびやかに飾られた言葉の裏にどんな醜い本性や欲があるのかを暴いていった。言葉がまさに彼の武器だった。2016/11/18
yasuhitoakita
4
世紀末ウィーン。ペン一本で権力に対峙したイケてるオヤジ、カール・クラウス一代記。舞台は世紀末ウィーンでありながら、クラウスが対峙した俗物たちって、現代日本にもごろごろいそうで(ほれ、おーさかでなぜか人気の某ごろつき政党とかとか)、俗物根性は永遠なのねという慨嘆ががが^^;著者池内氏の疾走するような文体も魅力な一冊。2017/06/27
ミコヤン・グレビッチ
1
「炬火」と題した個人誌を30年以上にわたり、900号(!)も発行した稀代の諷刺家カール・クラウス。アルファブロガーの元祖とでもいったところでしょうか。本書では、青年時代にこの人物の研究に打ち込んだという池内紀さんの案内で、クラウスの残した仕事と、19世紀末からナチスドイツの台頭までのウィーンの時代背景を学べます。ジャーナリズムの本質とは何なのか。この本を読み進めながら、あれこれと考えさせられるところがありました。「こんな時代」にこそ読むべき1冊。 2019/02/10
iwasabi47
1
池内紀氏の若い頃に書かれた著作のようで、ウィーン世紀末の批評家カールクラウスの評伝。LWやフロイトが影響受けたらしいので手に取ってみた。当時ブルジョワジーの欺瞞を苛烈に一人ペンで戦い続けた。クラウスの批評の苛烈さをなんとか著者が読者に伝えようと熱くなってのが判る。やはりクラウスの文章に当ってみるのがいいだろう。2017/01/31
Orange
1
19世紀末ウィーンが生み出した頸烈な批評家の評伝。論争につぐ論争で敵つくりまくり、襲撃されること多数、しかし信条を曲げず雑誌を発行し続ける、いろいろと規格外な人。嫉妬してしまうぐらいにステキ。女性にたいして辛辣な警句も連発したが、一方で、ひとりの女性に宛てたラブレターが1065通残されていたりする。黒歴史だ…。「愛して、欺かれ、嫉妬する。さも道理か。ところでさらに不快なのは、嫉妬して、欺かれ、愛する!」このモテなさそう具合も完璧。2015/11/27
-
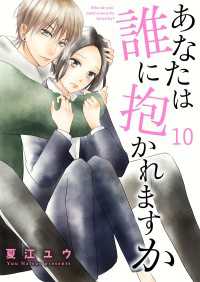
- 電子書籍
- あなたは誰に抱かれますか 10巻 Co…
-

- 洋書電子書籍
- ガロワコホモロジーと類体論(テキスト)…