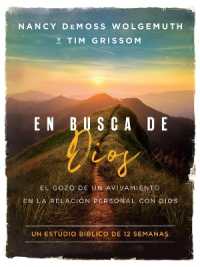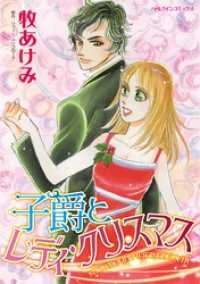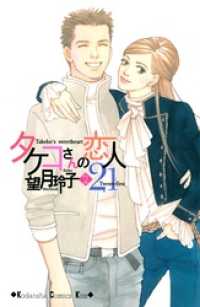内容説明
「家族にも極秘」を指示され、和光研究所の一室で研究が始まってから約30年。実際に本物の翼やエンジンを作った経験は皆無というエンジニアたちが、専門書を頼りに開発を始めた。まさに手探りだった。ホンダはなぜ空を目指したのか。高い壁をどう乗り越えたのか。二輪車メーカーとして出発したホンダが、ジェット機参入という壮大な野望を実現させた過程をひもとく。青山の本社から「金食い虫」と陰口をたたかれてきた若きエンジニアたちの苦闘を克明に描いたノンフィクション。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
たこ焼き
10
単なる思いつきではない創業者の想いによる長い人材育成が身を結んでホンダジェットはできた。本気でやるなら自分でやる。そのことにより知見はたまる。理論から積み上げるだけでなく、あるべき姿を考えてから理論で裏付けるのがよい。他人に迷惑をかけず、博打をやらず、時間を大切にせよ。長期的視野で見れる人と仕事をすること。親近感いうのは優秀ではなく欠点のある人に感じるもの。難しい複雑な調整は現場のテクノクラートだけでは判断できない。絶対的な存在が必要。2024/01/08
C-biscuit
10
図書館で借りる。前からホンダジェットのことが気になっていたが、やはり開発には多くの苦難や人間ドラマがあったのがわかった。ホンダはアシモのように突然自動車メーカーではないようなものを発表する。同じようにも思っていたが、ビジネスとして成立させるつもりもなく研究していたようで、この辺りが、時代とホンダの良さを感じさせる。本田宗一郎についてもかなり詳しく書かれているのも良い。近所に和光の研究所で働いている人がいる。嫁同士の話では、大した仕事してないようなことを言っていたが、秘密裏に面白い研究が進行中に違いない!?2016/04/08
trazom
3
ジェット機開発に賭ける男たち一人一人の魂が乗り移ったような熱い筆致が心を打つ上質のノンフィクションである。ホンダのエンジニアの熱意が、初めは見下した態度だったアメリカの技術者の心を動かすドラマも胸打つが、冷静な意味で、技術開発プロジェクトの進め方に対する示唆に富む内容が、この作品の深さを増している。合議制で皆が平等に情報をシェアする民主的な方法では、航空機のプロジェクトはうまくゆかず、一人の独裁的なエンジニアの意思決定に委ねてこそ開発が成就するのだという事実を、経営者とエンジニアはどうとらえたらいいのか。2016/02/21
たっつん
2
自動車メーカー・ホンダがジェット機を誕生させるまでの半世紀に渡る苦難の物語。「技術のHONDA」に脈々と流れるクラフトマンシップ。大きな光の先には暗く長い影がある。この手のノンフィクションにはつい引き込まれてしまう。2022/10/28
kentake
2
昨年12月に米国で型式認証を取得し正式に納品が開始されたホンダジェットの開発の歩みを纏めた本。 何もないところからジェット機を開発し事業化する難しさと、夢を諦めずにその困難を克服し実現してきた関係者の情熱が感じられる。従来の常識を超えた主翼上へのエンジン配置など斬新な技術への挑戦がデザイン的にも優れた製品を生み出した点は興味深い。それを可能としたのは、本田宗一郎氏が残したホンダのDNAなのだろう。2016/03/02