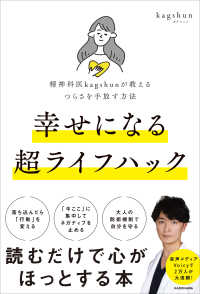内容説明
「差異」を生きる、とはどういうことなのか。ドゥルーズの単著を深く読み込んだ上で、「微分的なるもの」にその哲学の本質を見いだした、記念碑的名著。『差異と反復』は、たんに有名な現代思想の一つにすぎないのではない。分子生物学などの知見を取り込みつつ、「生きることそのもの」を哲学した傑出した著作なのだ。ドゥルーズの思考によりそい、新しい哲学と倫理のあり方を示した快著の文庫化なる! (講談社学術文庫)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
amanon
5
平明な文体で思いのほかさくさく読み進めることができたが、後書きにもあるように、著者がもともと理系志向だったため、特に前半は理数系の話が多く、理解の程はかなりあやふや。それでも、現在常識とされている多くのことについて、激しい憤りを覚えているということは理解できたか。その理数系のトピックの中でもとりわけ興味深かったのは、πについての論議。数学音痴の僕でも、このπの存在は以前から気になっていたので。それと印象的だったのが、著者が障害や、病人、ケアについて度々言及していること。この傾向を発展させると面白いかも。2017/01/31
Gakio
3
変な本だった。ドゥルーズの著作を直接説明する感じではなく、彼の著作を引用しながら小泉義之が語っている。微分方程式の説明から、遺伝子、進化論、HIV、安楽死や脳死判定、オゾン層破壊などの話。なぜか武田泰淳やトルストイなどが唐突に引かれる。自然科学のトピックを使って哲学的問題を思考するのがドゥルーズの方法なのね、とぼんやりだが印象付いた。 それぞれのトピックでかなり極論めいた書き方をしているので、書かれてることをどこまで信じていいのかが分からない。2025/05/06
なっぢ@断捨離実行中
3
すでに現代新書版で読んでた。痛恨。2017/07/09
multiplus
3
文体が好きではないけど、内容は好き。よいドゥルーズ解釈。まあ、ドゥルーズってそうだよねって感じ。個人的にはフーコーの章なのにほぼニーチェの話だったのが受けた。2015/12/25
ピリカ・ラザンギ
2
ドゥルーズの哲学的を知りたくて読んでみたものの、途中の三体問題にしても結局そこまでカオスではないというか冥王星は太陽系から飛んでいかないし(アトラクターの話あるけど安定している)、樹形図の種の分類もそこまで人類に恣意的でもない(個の話をしたけどプラトンで政治家とか医者とかの種から離れ無かったのはなんでだ)、生物循環も生活環とかアフォーダンスを考えるとそこまで批判対象か?という感じとかが高まって途中で読むの辞めてしまった。ドゥルーズがパラメータが沢山ある問題とか差異を扱っていたのはわかった。2019/07/11
-

- 電子書籍
- 今日から始める幼なじみ 9巻 バンチコ…