内容説明
名もなき工人が作る民衆の日用品の美、「民藝」。大正時代半ばから二十年近い歳月をかけて日本各地で手仕事の「用の美」を調査・収集した柳宗悦は、自然と歴史、そして伝統によって生み出される美を探求し続けた。著者がみずからの目で見、選び取った正しい美しさとはなにか。日本文化が世界的に注目される現代、今なお多くの示唆に富む日本民藝案内。
-

- 電子書籍
- 一目ぼれなんて【分冊】 4巻 ハーレク…
-
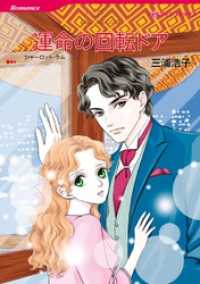
- 電子書籍
- 運命の回転ドア【分冊】 6巻 ハーレク…
-
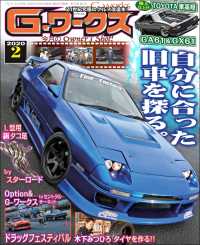
- 電子書籍
- G-ワークス 2020年2月号
-

- 電子書籍
- 甘く優しい世界で生きるには 3 MFブ…
-

- 電子書籍
- お見送りいたします 6巻



