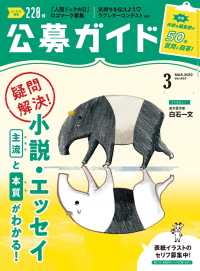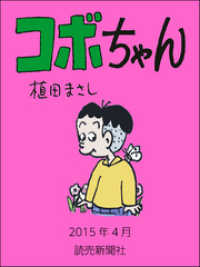内容説明
【2011年サントリー学芸賞[芸術・文学部門]受賞】そのサウンドと〈歴史〉はいかなる欲望がつくったか。ロック、ジャズ、ブルース、ファンク、ヒップホップ……音楽シーンの中心であり続けたそれらのサウンドは、十九世紀以来の、他者を擬装するという欲望のもとに奏でられ、語られてきた。アメリカ近現代における政治・社会・文化のダイナミズムのもと、その〈歴史〉をとらえなおし、白人/黒人という枠組みをも乗り越えようとする、真摯にして挑戦的な論考。(講談社選書メチエ)
目次
はじめに
第1章 黒と白の弁証法 ──擬装するミンストレル・ショウ
第2章 憂鬱の正統性 ──ブルースの発掘
第3章 アメリカーナの政治学 ──ヒルビリー/カントリー・ミュージック
第4章 規格の創造性 ──ティンパン・アレーと都市音楽の黎明
第5章 音楽のデモクラシー ──スウィング・ジャズの速度
第6章 歴史の不可能性 ──ジャズのモダニズム
第7章 若者の誕生 ──リズム&ブルースとロックンロール
第8章 空間性と匿名性 ──ロック/ポップスのサウンド・デザイン
第9章 プラネタリー・トランスヴェスティズム ──ソウル/ファンクのフューチャリズム
第10章 音楽の標本化とポストモダニズム ──ディスコ、パンク、ヒップホップ
第11章 ヒスパニック・インヴェイジョン ──アメリカ音楽のラテン化
注
Bibliographical Essay─参考文献紹介
あとがき
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
zirou1984
31
すっごい面白い。19世紀のミンストレル・ショウという「黒人の擬態をする白人」をアメリカのポピュラー音楽史における軸とし、ヒルビリーやカントリーミュージックからヒップホップまでの系譜を一本の線で結んでいく。音楽というのはどうしてもエピソードやイメージ先行で語ることに快楽が宿ってしまうのだけど、事実や先行研究を丁寧に掘り下げていくことで、そうした印象が常に後年からの解釈によって更新されていることがよくわかる。ヒスパニックの話からアメリカという存在自体の再定義を示唆する最後も刺激的。周りが名著と言うのも納得。2017/10/17
チェ・ブンブン
22
「ポピュラー音楽論」を教えてる教授の本。ヒップホップ史の復習ができ、レポートのいい助けとなった。しかし、ギャングスタものの定義がいまいちわからなかった~_~;2014/07/11
しゅん
19
二回目。やはりこんなに面白く学べる音楽書は他にない。アメリカのあらゆる音楽を「擬態の欲望」から解読していく展開がとにかく楽しいし、カントリーやR&Bといったジャンル分けがいかに政治的で恣意的なものかわかるのもスリリング。音楽書を超えたアメリカ文化論として秀逸。日本人なら読んで損はない一冊。2019/10/02
Ecriture
19
白人が黒人を演じたミンストレル・ショウに始まり、アメリカの音楽は自分ではない何者かを演じる「擬装」によって突き動かされてきた。アイリッシュが顔を黒塗りにして舞台に立つことで白人の仲間入りを果たし、ユダヤ系はその後黒人性を意識した音楽作曲によってアメリカ人に同化しようとした。ブルースシンガーは南部の貧しい黒人イメージを進んで引き受けてエレキギターを手放し、カントリーやフォークは反体制・反商業主義、ギャングスタ・ラップはギャング性を擬装した。音楽によって何者かへと変装することとその政治性が見事に論じられる。2013/11/03
1959のコールマン
18
☆5。もちろん凡百の音楽本からは抜きん出た書ではあるので5点満点。さて、他者への<偽装>というテーマでアメリカ音楽を分析しているが、成功したとは言いがたい。「それが何?」「ポピュラー音楽ってそういうもんじゃないの?」という思いが浮かび上がってきてしまう。ただ、興味深いと思ったのは最終章で、アメリカ音楽へのラテン音楽の影響が書かれている。ここをもっと深掘りしてくれれば「おお!さすが!」となったのに。そう思うのは私だけだろうか? 2019/05/07