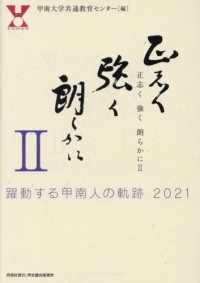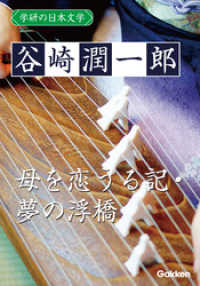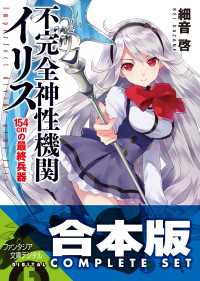内容説明
なぜみずから屈し圧政を支えるのか。圧制は、支配される側の自発的な隷従によって永続する――支配・被支配構造の本質を喝破した古典的名著。シモーヌ・ヴェイユが本作と重ねて20世紀の全体主義について論じた小論を併録する。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ehirano1
105
圧政が成立するのは支配者が原因ではなく、それに民衆が隷従するから。日本ではこれを「長いモノには巻かれろ」と云い、西洋では「自発的隷従」と云うらしい。一方で、支配者の支配戦略も心理を突いていて巧妙であることは数百年ほぼ不変で悪い意味で感服。であれば、これはもはや社会システムなので、これを受け入れ最善の道を探り続けるしかない、ということかな。2025/09/03
兎乃
32
スピノザやヴェイユ好きの身の上として、16世紀に18歳のラ・ボエシが記した本書を読むのは“今”と思う。とりあえず丸呑みして 吐き出されたものが醜い吐瀉物か それとも小さな珠か 時として動かぬ躰を持て余しつつ、ダ。不快を友に、孤独と自足を身につけたい。2015/10/20
シローキイ
30
恐らく初めて集団心理学に触れた本ではなかろうか。この時代にその事を研究する炯眼もさる事ながら彼が若干16歳から18歳の間にこの小論文を書いたのも彼の知性の卓越性を物語っている。封建的な社会構造によって自発的に服従をする国民は生まれ持ってして服従を教えられた者であるとの見解が記されている。2018/05/30
小鳥遊 和
27
訳者は翻訳に相当苦労したという。英現代語訳は読み易いので、原仏語が古いのが原因なのだろう。解説の対米従属批判はむき出しすぎるが、言語の所与性と政治的従属を関連づけた点は面白い。ヴェイユ筆の付録は示唆的で、著者の同時代人ガリレオによって物質的環境の力学的認識が発展したことの類比で、社会的環境で働く「力」概念の革新が必要と指摘する。マルクス主義は経済を研究したが、「欲求」の観念によっては不平等や経済的隷従という社会的現象は理解できず、社会的「力」の観念が不可欠だという。これは21世紀に重視されるべき卓見だ。2024/12/24
白義
27
支配者とは、支配する圧倒的多数の民衆よりも、本来か弱い存在だ。だから、娯楽をばらまき民衆に自ら自由を放棄させたり、自らの権威にへつらう取り巻きの小圧政者を用いながら「自発的に」自由を捨てさせるよう仕向けなければならない。自由という本性に代わり慣習の毒を注ぎ込み、別の本性を植え付けなければならないのだ。そう激烈に君主や権力者を批判するラ・ボエシが、その実人生に当たってはフランス王権の忠実な臣民であり、どうやら心の底からそれを信頼していたことが一見するとかなりミスマッチに見える2015/01/17