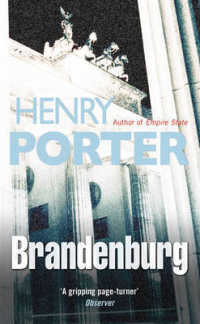- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
宮本常一の傑作『山に生きる人びと』と対をなす、日本人の祖先・海人たちの移動と定着の歴史と民俗。海の民の漁撈、航海、村作り、信仰の記録。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
-





まさしの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kinkin
95
じっくりと読むことができた。著者が多くの人達に海への関心、海に生きた人びとへの愛情と理解をもってもらうようにその歴史のごくあらましを描いた本。日本は大小たくさんの島で構成されている。各地域の海人のこと、彼らの生活・漁の特徴他多くの文献や現地での調査を基に紹介されていた。農業の一方で漁業国でもある日本について知ることができた。気になったこと・・・本種では古代から海の貝類(サザエやアワビ)を採ってきたとあるが古代の人は水中めがねのない時代どのようにして見つけ採ってきたのか気になった。他の書も読んでみたい。2018/01/11
nobi
79
この「海に…」には、姉妹書「山に…」にはなかった万葉集からの歌の紹介がある。詠み手は海人(あま)の姿は目にしても山の生活まで知る機会はなかったよう。で、猟と違って漁主体の生活は楽、海の広がりも風情ある生活を支えていた、が読み初めの感想。これは訂正が必要だった。海も相応に厳しい生活。夏、島に渡っての小屋暮らし、一つ処に定住できないがための漁場を求めての移動、応仁の乱後の困窮から生まれた海賊等々。遣唐使船に一回当たり二〇〇人程の海人が水夫として召集されていた、といった事情も知ると歴史の見方が少し変わってくる。2019/11/14
AICHAN
34
図書館本。同著者の『山に生きる人びと』を読んだので、ついでにこれも借りて読んでみた。私のイメージでは「山に生きる人」は縄文人の末裔であり、「海に生きる人」は弥生人の末裔に近い。魏志倭人伝の「沈没して魚鮑を獲る」という習性が弥生時代の倭人の姿と重なるからだ。しかし、この本を読んでそのようには分けられないことがわかった。狭い日本列島においては狩猟場所に限りがあり、漁労のほうが生業としては適しているという。縄文時代後期に狩猟に限界が来て漁労に従事する人が増えたという説には納得がいった。2018/01/26
gogo
19
海の民の社会史。この本を読んで、日本では中央政権の力が弱まると漁民の移動性が高まり、逆に中央集権が進むと漁民に定住の圧力がかかる歴史の傾向があることを知る。しかし、漁民は自由に移動することを好み、すでに秀吉の治世に泉佐野の漁民が対馬へ漁へ出かけたりしている。あと、漁民や水夫の間では長幼の序よりも、実力主義が尊ばれる説明のくだりが新鮮だった。若い頃に財を成したのに、年老いて零落した古老の実例が挙げられている。陸史中心観に慣れている我々に、異なる視点から歴史を見ることの大切さを教えてくれる一冊だと思う。2017/08/05
T M
15
宮本先生の民衆史の一つ。長崎県五島の寺の過去帳に瀬戸内や近畿の死亡者が数多く記載されていることから、かなりの人の移動があったことを思わせるドラマチックな記述で始まる。中世〜江戸時代までの主に内海の漁民の成り立ち、変遷(漂流、定住し半農化、商船化など環境によって異なる選択をしていった様を詳述している)を軸に、漁の方法や文化をまとめた傑作です。あとがきにもあるのですが、日本は、祖先が海人であるのに、海への関心が薄い。日本の一側面を形作った人々へ少しでも理解や敬意を示せるような、そんな著書です。2017/08/21