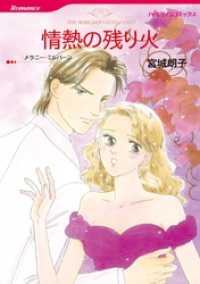内容説明
近江の琴糸、月瀬の奈良さらし、越後の筆匠、佐渡の人形遣い、雪の中の瞽女たち、信濃の山蚕、忘れられた巨桜たち……。昔ながらに手間と日数をかける職人の精緻な手仕事と、日本の山野の美は、まさに滅びようとしている。各地を訪ね、痛恨の思いと復興への願いをこめて書きしるす、記念碑的ルポルタージュ16章。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
shizuka
58
失われ往く江戸を懐古するのが永井荷風ならば、失われ往く物や伝統を惜しむのが水上勉である。取材をされている当時が昭和40年代頃。この時ですでに古き良き伝統は風前の灯。水上氏の愁嘆も行き場がなく、吐息とまじり空に散ってしまう。易きに流れ、量産の時代にだんだんと移ろいゆく現状、見るに見かねて日本伝統工芸の職人を巡る。職人たちはもう諦めの境地。いくら無形文化財に認定されようとも、政府が保護するわけではない。唯一、皇室がその火を絶やさぬよう目を掛けているという。皇室、日本の心。最後の砦は皇室にあるのかもしれない。2016/10/03
S.Mori
25
作家の水上勉が全国の伝統工芸の伝承者のところを回ってまとめたルポルタージュです。情感あふれる文章で職人たちの手仕事を描いており、一読深い印象を残します。お金を儲ける事ばかりを考えずに、使い手のことを第一に考えて工芸品をコツコツ作る職人たちの生きざまに魅せられました。これは昭和の頃の記録なので、もうなくなってしまった工芸品もあるかもしれません。京菓子のことも書かれていて、大学時代によく食べに行った今宮神社の炙り餅のことが懐かしかったです。2020/08/12
さっと
7
タイトルどおり、失われゆくもの―跡継ぎのいない手工業や量産と安価の波にかきけされていく伝統工芸などのルポ。雑誌に連載されたのが1967年で、その取材に約2年かけたということだから、描かれている職人の姿は今から半世紀も前のもので、多くのモノ、コト、ヒトがなくなっていることだろう。大量生産、大量消費の中で生まれ育ってきた世代としては、今では、なになに保存協会や郷土資料館でしか見ることのできない、昔は身近にあった民具に想像を膨らますばかり。その時代の職人さんと我々ハタラキバチの時間の使い方の差異がすさまじい。2014/10/29
marukuso
1
各地方にあった職人仕事はもはや機械にとって変わられてしまった。この流れは止まらないし、変えられないと思う。機械にでもできる仕事ではあるが人間にしか込められない思いであったり細やかなこだわりであったりと大切なものまで画一的に消え去ってしまうのはとても悲しい。そしてそういった簡単には測れない価値を大切にしたい。過去、人間がつくれたものが現在の人間にはつくれないという逆説はこれからの時代を考える上でも大事な視点だなと思う。2023/03/01
Quijimna
1
民具、郷土玩具を作る人、瞽女……。まさに現代日本から失われつつある生き様や情景を訪ねて記した旅のルポルタージュ。杉本ハルの名を懐かしく読んだ。風景も記憶も、放っておくと簡単に消えてしまうはかなさがある。★★★☆☆2011/09/28