- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
脳科学が明かす日本語の構造。英語で“I love you.”とは言っても、日本人は決して「私はあなたを愛している」などとは言わない。「雨が降る」を英語で言うと、“It rains.”のように「仮主語」が必要になる。――これはどうしてか? 人工知能研究と脳科学の立場から、言語について実験と分析を重ねてきた著者が発見した新事実。それは、日本語の音声がもつ特徴と、主語を必要としない脳の構造とが、非常に密接な関係にあることだった。斬新な視点による分析と、工夫をこらした実験、先行研究への広範な検討を重ねて、主語をめぐる長年の論争に大きな一石を投じる、衝撃の書! (講談社選書メチエ)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
チャーリブ
48
著者は工学博士。表題の「日本人の脳に主語はいらない」という新説を脳の機能や著者の持説である「仮想的身体運動」理論から説明しています。日本人は母音を左脳(優位)で聞いているそうです。母音を言語野のある左脳でダイレクトに聞くことができる日本人には主語は不要という議論ですが、どうでしょうか。むしろ「想像とは仮想的身体運動である」とか、「心とは複数の人間のあいだで作用する相互作用である」(つまり一人の人間の中には見つからないが存在していないとも言えない)といった話のほうを興味深く読みました。○2022/12/10
アルカリオン
11
部分的には面白いところもあったが、「畑違いの分野で奇抜な主張を唱えている」という印象。中盤以降、内容が散漫で「何についての本だっけ?」となるところも▼著者はfMRIを用いた実験等により脳機能を研究するのが本職のようだが、中途半端な理解に基づいて言語学的な新説を打ち出しているように見える▼主語が必須の言語(例:英語)とそうでない言語(例:日本語)というのは目新しい話ではなく異論もないが、イタリア語を後者に含めているのは、言語に対する理解が表層的だと思う。2025/06/15
清水勇
5
「この本の後に、右脳と左脳」を読んだが、逆にすれば理解度はもっと深められたかな? 前半は「仮想的身体運動」(人間は言葉を理解する時、仮想的に身体を動かすことでイメージを作る)の説明。人は模倣を通して自己を形成する。即ち、他人の心を模倣することで、自分の心ができ、自他を区別する ⇒ 「人は自分の心は人の心ほど理解できない。」は驚き。人は言葉を話す際に、脳の中の運動野を活性化させる。その活性化方法が日本語を母語とする人と、それ以外の人は異なることから、何故日本語で主語を使わないかを説明。難しい。再読要。 2015/05/20
かやは
5
言語の違いで脳が言葉を認識する道のりが違うということ。言語が違えば物事の捉え方が変わるということ。メタファーの使い方も、日本語は存在のメタファーが多く、英語は擬人のメタファーが多い。日本語で英語を理解するのは難しいことなんだと改めて思った。言語を学ぶ際は、その言語が物事をどういった面から捉えているか把握すると理解が早いのかもしれない。2012/09/13
みそさざえ
4
日本語の主語を考えるために、引き続き読んだが、科学的に分析が苦手で少々難解。でも、主語や人称代名詞と脳との関係は、おもしろいし、言語によって脳の使われる場所が違うというのは、とても不思議。臨界期が過ぎてからL2がいくら上達しても無理なのか? バイリンガルの場合は? どちらの脳が働くかで、感じ方も変っていくのか??? 興味はつきないが、とっつきやすい解説本が必要。2015/08/18
-

- 電子書籍
- 会社四季報プロ500 2024年 夏号…
-

- 電子書籍
- 顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君【分…
-
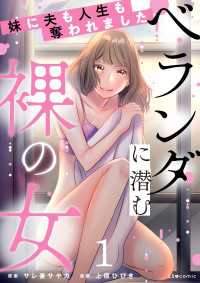
- 電子書籍
- ベランダに潜む裸の女 妹に夫も人生も…
-
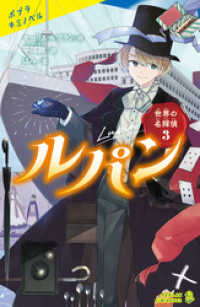
- 電子書籍
- 世界の名探偵3 ルパン ポプラキミノベル
-
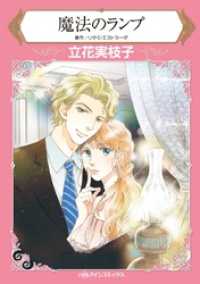
- 電子書籍
- 魔法のランプ【分冊】 10巻 ハーレク…




