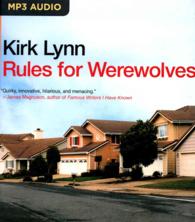- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
「安くて便利で消費者のため」のその先は? 百貨店、地方と都会、戦前の通販の黄金時代、商店街と地域、スーパーと消費者革命、家族経営が基本の、日本型コンビニの誕生と進化。1900年代から現代まで、日本人の買い物の歴史から考える。(講談社現代新書)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アナクマ
37
そそるタイトル。国際比較において「メーカーと小売業者との間に、多くの卸売業者が介在し、小規模小売店も多い」日本型流通。80年代まではさまざまな小売業態が共存したが今は…。◉商店街が寂れることに〈悲しい〉という声があがるのは何故か。消費・労働・地域という(とても気になる)3軸を立て、5つの業態(百貨店・通販・商店街・スーパー・コンビニ)を順番にそれぞれ俯瞰し、歴史学者が論じる『日本型流通の近現代史』。さて、商店街は必要なのか。なぜそのように思うのだろう。2024/04/11
1.3manen
36
ボン・マルシェ(1852年)が世界初の百貨店(33頁)。日本の通信販売は明治時代から(86頁~)。1876年津田梅子の父仙がトウモロコシ種子の通信販売。ダイエー中内功の流通革命(182頁~)。消費者の正しい選択こそが、日本から欠陥品や不良品を追放し、メーカーに製品改良を促す(220頁)。ファミマでは同居する夫婦、親子、兄弟、3親等以内の親族を対象とした家族加盟促進制度を設けた(238頁)。セブン-イレブンを巡る裁判で、本部は、コンビニ会計のうまみを維持するために見切り販売を阻止(274頁)。2016/01/27
雲をみるひと
33
戦前から現在までの流通業の変遷を百貨店、通信販売、商店街、スーパー、コンビニなどのテーマ別に論じたもの。各論的な構成だが、社会情勢と流通業の変遷など総論的なテーマもカバーされている。全編にわたり詳細な記載、丁寧に分析されていることに加え、冒頭にとっつきやすいテーマである商店街の地位の変化から見る日本の流通の現状を論じているように構成も工夫されている。良本だと思う。2021/10/12
バトルランナ-
27
題名に騙された棚に直行。『商店街って必要なの?』と思ってる人が買います。クラス会の運営は地元商店街の2代目に託してるしなあ。嫁の実家も商店街だし。おしんでスーパー出店にあたり商店街の大反対にあってたけど1980年代前半まではそれぞれ発展してたんだねえ。p17。三越が下足預りを廃止したのは1925年。p51。松坂屋って名古屋本店。p61。スーパーの発展は銀行融資ではなく、『回転差資金』。仕入れ代金の支払いは60日後。平均9.3日でうる。p202。平成不況がパートを創造した。p216。米国のセブンイレブンは2015/09/26
hk
26
これは良著である。「商店街はなぜ滅びるのか(光文社新書)」も併せて読みたい。相乗効果で流通にかんする造詣が深まること請け合いだ。 百貨店⇒通信販売⇒商店街⇒スーパー⇒コンビニと5つの章で構成されており、小売りの主役の変遷とその道理がよくわかる。わけても1920年代においては通信販売が小売りのメインストリームであり、出版社が通販事業も営んでいたというのは示唆にとむ。この事象は現下においてアマゾンという広告仲介業者がネット通販を兼業していることと相似形ではないか。やはり情報の担い手が小売りでは有利となるのか…2018/10/12
-
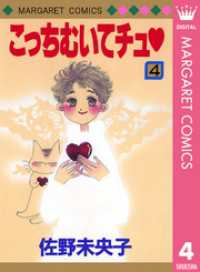
- 電子書籍
- こっちむいてチュ 4 マーガレットコミ…
-
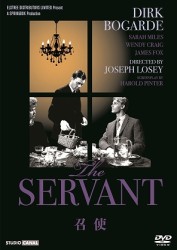
- DVD
- 召使