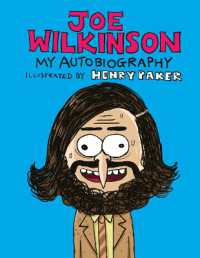- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
市場の力を活用すれば、日本は再生できる! JAL、ダイエーなど、企業再生の修羅場を知り尽くした著者が、ブラック企業・ゾンビ企業の淘汰から始まる日本再生の処方箋を説く。真の改革のチャンスは危機の最中か直前にしかやってこない。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
79
「選択と捨象」という題名がユニークですが、これには著者の考え方が反映されているようです。「選択と集中」とよく言うが、「選択」したうえで選ばれなかった事業や機能を「捨てる」ということでこのような題名になったようです。産業再生機構のCOOを務めた経験から「カネボウ」、「ダイエー」、「JAL」などの実例を詳しく説明してくれます。最後に大学教育での「実践的な職業教育」、高等教育でのアカデミックスクールとプロフェッショナルスクールの「二山構造」ということを考えるべきである、というのは考える価値あるものだと思います。2015/09/14
Hiroo Shimoda
9
何を捨てるのか、いかに捨てるのか。合理✖️情理の両方の能力が必要。納得感ある。外部から働きかけると合理は使えるが情理が使えないんだよな…2021/04/13
雲をみるひと
9
実例を交え企業再建を論じたもの。初出が一般紙連載ということもあり、各事例において詳細な記述まで踏み込まれていない印象はあるが、事業単位で捉える考え方はよく解説されていると思う。2020/05/28
miso soup
4
日本的「ムラ社会」企業から脱し、合理に沿って事業の切り分けを行うことが重要。事業が残るのであって会社はそれを営むための箱に過ぎない。一社一社が、会社としての価値を最大限高めるために、不必要な事業は捨てていく、社会全体としても、会社の新陳代謝を促していく、今の日本社会も変わらず残っている課題だろう。2024/04/27
Kentaro
4
ダイジェスト版からの要約 当時41歳の知識賢治氏が2004年5月、カネボウから離れて発足したカネボウ化粧品の社長に就任。振り返ってみると、カネボウの再建にとって、若いトップを内部昇格で化粧品会社の社長に就任させたのは大きな転換点だった。赤字の繊維部門から切り離した事もあり、「頑張れば自分たちに返ってくる」という組織に転換していった。「捨てる」決断はボトムアップでは出来ず、トップリーダーの判断だ。「やるべきこと」と「やれること」、「やりたいこと」。の3つがシンクロすると、組織はすごい勢いでドライブがかかる。2018/04/19


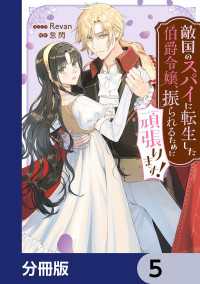
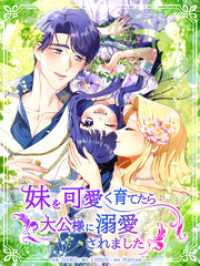
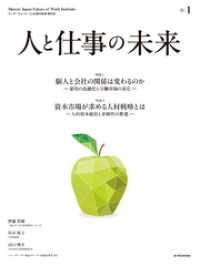
![コロナ禍という戦災――戦争とプロパガンダ:作られた[物語]を超えて](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-1052233.jpg)