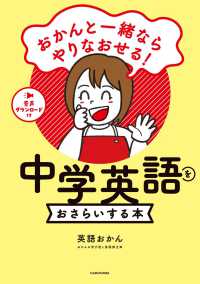内容説明
廃線の危機を乗り越え、ローカル鉄道の雄として異彩を放つ江ノ電(江ノ島電鉄)前社長の初著書。テレビなどでも注目度の高い江ノ電についてのマネジメント側からの初めての出版物となる。
全区間わずか10km15駅のローカル私鉄でありながら、年間乗客1700万人(うち1200万人超が観光客と推定される)以上を引きつけるのはなぜか?
その背景には、地域の魅力もさることながら、効率化の風潮に流されずあくまで「安全」を第一に考える「昭和の鉄道屋の心」や、「変わらないことの魅力」を打ち出す戦略があると著者はいう。
具体的には、トップが自らの脚で全線を歩く年末の総点検や、手間をかけても古い車両や駅舎を使い続けるエピソードなどが語られる。
米国流の収益重視の経営が全盛の中、あえて日本の良き精神文化を見直すことが重要だという思いが伝わってくる。
今後、量的な拡大が図れない中で、いかに「質」で企業価値を高めるか――という経営哲学としても大きな示唆を与えてくれる。
鉄道、観光、町おこしなどの関係者はもちろん、一般のビジネスマン、経営者にも新たな視点を与えてくれる1冊。
◆著者の言葉
江ノ電に昭和の良き姿を見出すことで、今の経済が置き忘れている大切な日本の精神文化を復権すれば、日本社会の再生の一助となるのではないか。
鉄道屋として生きてきた男の言葉も、今の時代にお役に立てるのではないか。
――おこがましいですが、そう考えて、鉄道のことを語る本を出させていただきました。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
なかしー
54
読書会に向けて再読。 鎌倉愛、江ノ島愛、江の電愛と言うガソリンをエンジンであるハートに流し込んで、熱意として爆発させる。 本文にある「江ノ電そのものがエンターテイメント」と言うワードに震えた。 鎌倉・湘南エリアと言うテーマパークに走る電車、それが江の電だ。2019/11/23
おいしゃん
49
鉄道好きとして、同業者として、楽しく読めた。しかし、タイトルの奇跡、とはなんだろうか?著者の安全への想いや、自社線ファンを増やす心意気は鉄道員として当然のことだし、奇跡的なV字回復の経営手腕を振るったわけでもない。それよりも、天下る前の小田急時代に取り組んだ数々の難工事やプロジェクトについての本を書いた方が、よっぽど読み物として面白かった気がする。2017/08/06
なかしー
17
湘南好きの私には湘南行ったら必ずお世話になる「江ノ電」。 私にとっては、遊園地のレトロなアトラクションみたいな感覚。 長谷寺~極楽寺にかけて、夏には両側道に地盤安定化の為の植えた鮮やかな紫陽花達で彩られるトンネルに通過する至福の一時。 稲村ヶ崎~七里ヶ浜区間の住宅街から国道134線に出る瞬間に世界が拓けるの解放感等々その場の情景が浮かび上がります。 それと合わせて、潮風による塩害、住宅街を通る為入り組んだ路線になり特殊なレールを敷く所もあり、保守点検の難しさ等を江ノ電の魅力がぎゅっと詰まった本。2018/08/30
かやは
11
普段を保つためには、普段以上に気を使うことが大切。鉄道は生き物、時を経て変化するものは、みんな生き物。海の近くを走っているから、一日電車を走らせないとレールが錆びてしまうこと。民家と隣接いているから、そこから延びる枝に注意しなくちゃならないこと。江の電の路線には、日本の鉄道で一番急なS字カーブがある。カーブを作るにはレールを短くして繋ぎ合わせなければならないが、レールの継ぎ目は電車にとって一番の弱点。もともと現場にいた社長だから、現場のことがわかっているんだと感じた。2016/04/29
里山輪太郎
4
江ノ電前社長であり、土木が専門の著者の目線から江ノ電を語っている。なるほどと思わせる内容盛りだくさん。鉄っちゃんには目から鱗だと思う。保守、点検の必要性、大切さがよくわかる。2017/10/22
-

- 電子書籍
- GoodsPress2022年1・2月…
-
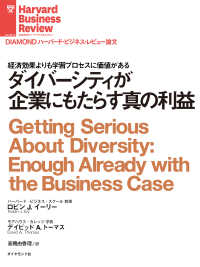
- 電子書籍
- ダイバーシティが企業にもたらす真の利益…