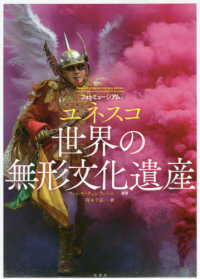内容説明
663年、倭国大敗。国家存亡の秋(とき)。後進性を痛感した倭は、国家体制の整備を急ぐ。対唐防衛網の構築、亡命百済人による東国開発、官僚制整備。律令国家「日本」完成へといたる、古代の「近代化」を描き、あわせて現代におよぶ、無策、無定見の日本外交の問題点を抉る。(講談社選書メチエ)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
isfahan
5
『天智と天武』の参考図書として読もうと思ったら森先生、マンガの監修もしてらしたそうで…。偶然。飛鳥時代の外交関係描写が詳細にかかれていて、勉強になった。白村江はやっぱり古代史の大きな曲がり角なんだなあ。この敗北の上に築かれるのが律令国家で。著者が暗に、近代史の情勢とかぶせているのもわからないでもない。2015/09/26
ながぐつ
1
20世紀末の日本と古代日本を重ね合わせて、日本の外交姿勢が「普遍性」を欠いて場当たり的で、特に唐に対して二重姿勢(事大と自尊)をとっている事を否定的に捉えているが、新羅も高麗も基本的には二重の姿勢(内外で使い分ける)を取っており、果たして日本のみが外交の変容に付いていけなかった訳ではないので、やはり疑問符がつく。2025/04/17
ナオ
1
たった2日の戦争がその後の日本の外交に大きな影響を与えたことが良くわかった。壬申の乱についても読むべきかな。2010/12/22
鐵太郎
0
「白村江」とは、「はくすきのえ」というより「はくそんこう」と読むのがメジャーらしい。古代日本が、武力のある蛮人として文明国家のシッポである朝鮮の政治情勢に介入し、敗退したのがこの戦い。これによって古代社会がどう変貌したのか、読んでいて楽しかった。2007/07/28
sa10b52
0
面白い歴史!一国の歴史は同じことの繰り返しばかりだと思うのだけど、統一されると外向きになる中国大陸、分かれてばかりの朝鮮半島、外交音痴の状態で介入すると失敗して内向きの発展に勤しむ日本というのは、二次大戦・冷戦そして今日に至る極東の歴史の原型のように見える。一方で戦後"日本"は天皇の独自性を出しつつ唐に配慮しながら実利を求めるなどしたたか。朝鮮は文化的には進んでいる面もあるが、分裂と近隣の強国によって後ろ盾を求めなくてはいけない構図が苦しい。少し古い本なので最新の説はどうなっているのだろう。2024/09/14


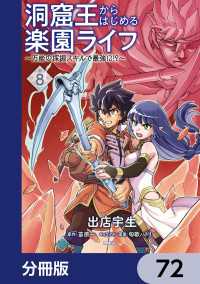
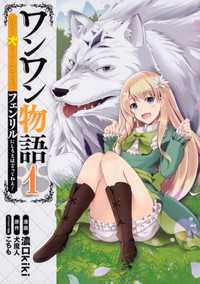
![モーニング 2020年19号 [2020年4月9日発売]](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-0845598.jpg)