- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
ありそうでなかった声にまつわる疑問集。声帯はもともと呼吸をしたり、食べ物をきちんと飲み込むための安全弁だった!? 毎日発している声なのに実は知らないことだらけ。なぜ人によって声はちがうのか、なぜ赤ちゃんは泣きつづけてものどが平気なのか、ささやき声は声帯によくないのか、太っている人のほうが声がよくでるのか。声にまつわる基本知識の集大成。(ブルーバックス・2012年3月刊)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kaizen@名古屋de朝活読書会
21
#感想歌 声帯と病気と悩み解消法発生からくり声を育てる 取材先、参考文献、索引と監修者あとがきもついている 音痴には聴覚記述ありました。人工声帯なども欲しいね。2017/09/30
calaf
11
声っていろいろ深いなぁ...声帯や咽喉、咽頭などだけではなく、それこそ全身を使って作られているのが声。その全身のパワーを声に反映させる事の出来る人が、良い声の人という事らしい...2012/07/03
和草(にこぐさ)
5
仕事の関係で知りたかった内容がどっさり。とても勉強になりました。病名の違いもわかり納得。2016/10/25
アルカリオン
2
雑学的なQ&A集であり「事典」という感じではないが、ざっと読むには悪くない。興味深かったのはp124。「邦楽で高い声のことを『甲』という。『甲高い声』というように昔の日本では高い声は好まれなかった。一方、低い声は『乙』と言い、ほめ言葉であった。『乙な声』は魅力のある声の意だった」確かに「甲乙」のうち、格上・上質なのは甲のはずなのに、いい意味の慣用表現としては「乙なもんだ」のように乙が出てくる。こういう背景があったのか。2018/07/17
fu-ko
2
色々参考になりました。ささやき声が声帯を傷めるとは以外。2016/09/28
-
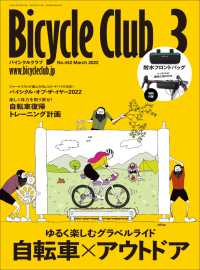
- 電子書籍
- Bicycle Club 2022年3…
-
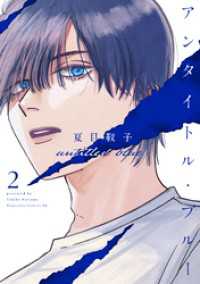
- 電子書籍
- アンタイトル・ブルー(2)
-
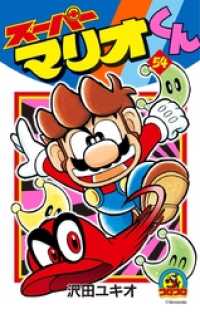
- 電子書籍
- スーパーマリオくん(54) てんとう虫…
-
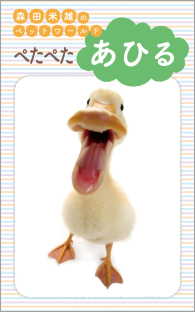
- 電子書籍
- ぺたぺたあひる
-

- 電子書籍
- 死体は悩む 多発する猟奇殺人事件の真実…




