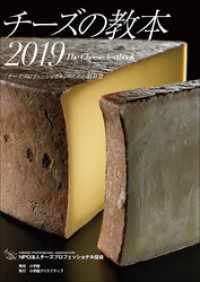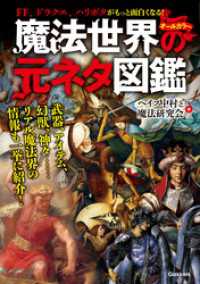内容説明
「日常会話」や「雑談」は得意でも「対話」は苦手なことが多い日本人。ふだん同じ価値観の仲間とばかり会っているので、異なるコンテクストの相手と議論をしなくて済んでしまう。文化の違う相手と交渉したり共同作業をする経験が、まだ日本人には少ないのだ。さらに携帯電話などの登場で、世代間のギャップが広がる。それではどのようなスキルが必要なのか。豊富な具体例をもとに、新しいコミュニケーションの在り方を真摯に探る。(講談社学術文庫)
目次
学術文庫版まえがき
話し言葉の地図
電脳時代の対話術
っていうか……
過ぎたるは及ばざるがごとし
なんでやねん
ヒトとサルのあいだ
単語で喋る子供たち
「ここ、よろしいですか?」
畳の上では死ねない仕事
コンテクストのずれ
「ネ・サ・ヨ運動」と「ネ・ハイ運動」
顔文字は世界を救うか?
ひよこはどこのお菓子か?
半疑問形の謎
日本語はどう変わっていくのか(一)
日本語はどう変わっていくのか(二)
日本語はどう変わっていくのか(三)
フランス人との対話(一)
フランス人との対話(二)
敬語は変わる
ため口をきく
対話のない社会(一)
対話のない社会(二)
対話のない社会(三)
対話のない社会(四)
対話をはばむ捏造と恫喝
新しいアクセントの世界
英語公用語論
悪口言い放題社会
ふたたび英語公用語論について
対話という態度
二一世紀、対話の時代に向けて
あとがき
解説──来るべき社会 高橋源一郎
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
佐島楓
72
実際に連載されていた期間は二十年ほど前。それくらいの時間でも日本語は揺れ動いていることがわかる。若者言葉、ネットスラングと当時最新の言葉を考察しながら、コミュニケーション、ディスコミュニケーションの補本質を探る姿勢が、言葉を扱う人間はかくあるべしと思わせるもので、とても共感できた。2019/08/23
金城 雅大(きんじょう まさひろ)
35
1997年から2000年にかけて連載されたエッセイであるにも関わらず、核心の内容は今読んでもじゅうぶんにリーダブル。これは素晴らしい。いわゆる「若者世代の日本語の乱れ」と呼ばれるやつにだいぶ寛容になれる。(今だと「わかりみ」とか「エモい」とか?)以前読んだ『日本語が亡びるとき』に通じる。2019/11/20
Akihiro Nishio
28
週末のシンポジウムに向けてオリザさん本3冊目。2015年初刷りになっているが底本は2002年の発刊で、1998年から2000年にかけて連載されたエッセイ集であった。したがって時事ネタはどうしても古い。読んで感じたのは、若い時に韓国に出たことで、言葉、コミュニケーションに対して非常に鋭敏になり、ずっとそんなことを考えているんだなということ。また、オリザさんの戯曲のネタも、そうしたコミュニケーションのずれをテーマにしているんだなということ。普通の劇作家が個人的な心理的課題をテーマに執筆するのと根本的に異なる。2019/05/09
りえこ
25
言葉やコミュニケーションについて色々考えていて、興味があり読みました。時代や世代にもとても関係がある。対話をきちんとしていきたい。2016/07/11
yukiko-i
25
劇作家である平田オリザさんだからこそ、言葉の一つひとつが持つ意味合いに敏感で、相手に想いを伝えるにはどう対話すればよいのか、わかりやすく書かれ読みやすかった。15年くらい前に書かれたエッセイが今にも通じるところがあり、本質は変わってないと感じた。2015/08/04


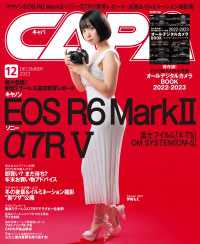
](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-1134575.jpg)